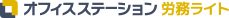お役立ち情報
離職票とは?離職証明書・退職証明書との違いや書き方など手続き方法まとめ
社労士の声から生まれたソフトだから使いやすい。オフィスステーション 労務で
入退社手続きや有期雇用の更新手続きなどの様々な労務手続きを効率化!
⇒【公式】https://www.officestation.jp/roumu/にアクセスして製品カタログを無料ダウンロード
こんにちは。人事労務クラウドソフト「オフィスステーション 労務」のお役立ち情報 編集部です。
離職票は従業員が退職した際に扱う書類です。離職票と混乱しやすい離職証明書・退職証明書との違いや、従業員が退職した後の離職票発行までの流れ、提出先や提出期限など離職票発行に必要な知識をまとめました。
- 離職票とは何か、内容・提出期限・提出先などまとめ
- 離職票を発行してもらうまでの流れと発行に必要なもの
- 離職票の書き方
- あると便利な様式テンプレート
目次
離職票とは?
離職票は、会社の従業員が退職したときに会社から渡す書類の一つで、正式名称を「雇用保険被保険者離職票」といいます。退職者が失業給付(基本手当)を受けるためにハローワークに提出する必要がある書類です。使用者である会社は、退職する従業員が離職票の交付を希望する場合に、離職票を交付する義務があります。また、59歳以上の退職者に対しては必ず発行しなければなりません。
参考:雇用保険法施行規則17条
離職票・離職証明書・退職証明書の違い
離職票とよく似たものに「離職証明書」「退職証明書」があります。いずれも言葉はよく似ていますが、内容としては別物です。
離職票と離職証明書の違い
離職証明書は、離職票を発行してもらうために、会社がハローワークに提出する書類を言います。離職票と離職証明書の関係は以下のとおり。

離職証明書は3枚つづりになっており、1枚目が「事業主控」、2枚目が「安定書提出用」、3枚目が「退職者交付用」で構成されています。離職証明書をハローワークに提出すると、離職票-1が交付されます。離職証明書の3枚目は離職票-2にあたるため、会社は1と2の両方を退職者に交付します。
なお、離職証明書の記入用紙はハローワークに用意されており、Webからダウンロードすることは基本的にできません。ただし、政府が開発する電子申請ソフト「e-Gov電子申請」では、以下の申請画面を通して手続きが可能になるので、ハローワークに出向く手間を省けます。

出典:e-Gov電子申請
退職証明書とは
退職証明書は、従業員が会社を退職したことを示す書類で、退職者が国民健康保険に加入する際に必要になります。また、退職者が新たに就職する際に就職先に求められることもあります。会社は、退職者から請求された際に退職証明書を発行しなければなりません。
退職証明書は厚生労働省のWebサイトからテンプレートをダウンロード可能です。

離職証明書(離職票-2)の書き方
離職証明書を作成する際には、慣れていないと何をどこに書き込めばいいかを悩むものです。以下に離職証明書の記入で悩みがちなポイントと、記入内容をまとめました。
離職証明書の様式と記入内容

- 1.被保険者期間を算定するための期間。離職日から1カ月ずつさかのぼり、下記に該当する月が12カ月以上になるまで記入します。(さかのぼれる最大は原則2年間まで)
- 2.賃金支払い基礎日数、つまり「1」の期間に、出勤や有休などで賃金の支払いが発生した合計を記入します。
- 3.1行目に離職日からさかのぼって直近の賃金締め切り日の翌日~離職日を記入します。2行目以降は1カ月ずつさかのぼって前月の賃金締め切り日の翌日~賃金締切日を記入します。
- 4.「2」と同様に対象期間の日数を記入します。
- 5.月給の場合は「5」に賃金額を記入。時間給・日給・出来高制の場合はその隣の「B」に賃金額を記入。
- 6.「2」「4」が10日以下で80時間以上ある場合は時間数を記入。
- 7.該当する離職理由に「〇」をつけます。
- 8.離職理由を具体的に記入します。
賃金支払い基礎日数とは?
「2」の枠に記入するものを、被保険者期間算定対象期間のうちの「賃金支払い基礎日数」と呼び、基本的には給与の支払い対象となっている日数のことをいいます。賃金支払い基礎日数は会社の給与制度により異なりますが、その日に1時間でも出勤していれば「1日」と数えます。
基礎日数の数え方
完全月給制の場合:月間すべてを拘束する意味の月給制で、欠勤日を控除しないのであれば暦日数が基礎日数となります。
日給月給制の場合:月給制ではあるものの、欠勤日については控除される給与の場合は「暦日数-欠勤日数」が基礎日数となります。
日給制および時給制(パートタイム・アルバイトなど)の場合:出勤日を賃金支払い基礎日数とし、有給休暇などについては加算します。
参考:被保険者についての諸手続
離職票を発行するときに必要な書類
離職票発行の際、会社は離職証明書と併せて「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出します。雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員が雇用保険の被保険者資格を失ったことを届け出るもので、離職票の発行有無にかかわらず、会社は必ず作成して提出しなければなりません。
なお、雇用保険被保険者資格喪失届は以下のハローワークのWebサイトからダウンロードできるほか、電子申請も可能です。

また離職証明書を提出して離職票の発行を受ける際には、離職の事実や離職理由を証明するための書類が必要です。どのような書類が必要になるかは、離職理由によって異なります。以下が必要書類の一例です。
| 離職理由 | 必要書類 |
|---|---|
| すべての人 | 賃金台帳または明細書 出勤簿またはタイムカード 労働者名簿 |
| 自己都合の場合 | 退職願・出勤簿など、離職理由が確認できる書類のコピー |
| 解雇の場合 | 解雇通知書など解雇理由を確認できる書類のコピー |
| 退職勧奨の場合 | 退職願など離職理由が確認できる書類のコピー |
| 定年の場合 | 就業規則・再雇用にかかわる契約書など離職理由が確認できる書類のコピー |
| 契約期間満了の場合 | 契約書など離職理由が確認できる書類のコピー |
離職証明書の提出先と提出期限
離職証明書は雇用保険被保険者資格喪失届と併せて提出するものですが、雇用保険被保険者資格喪失届は従業員の退職日の翌々日から10日以内に提出します。このため離職証明書の提出期限も「従業員の退職日の翌々日から10日以内」といえます。
また3枚つづりの離職証明書のうち、最終的に回収されるのは2枚目ですが、事務所管轄のハローワークへの提出は、3枚いずれについてもおこなわなければなりません。このほか、e-Govで電子申請することも可能。e-Gov電子申請には、ハローワークに記入用紙を取りにいかなくともよいという点で利便性があります。
離職票まとめ
離職票の作成は、記入用紙の入手や賃金支払い基礎日数の確認など手間がかかります。そのうえ、会社から退職者が出る度におこなう繰り返し作業であるため、従業員数が多い会社では年間を通した作業量が膨大になることも。
離職票に係る作業を効率化する方法にはe-Govの使用をはじめとする電子化が挙げられますが、e-Govは無料である半面、大きく作業を効率化できないという声もあります。
そこで、国はe-Govをさらに効率化するソフトを開発できるよう「外部連携API」というツールを民間企業に提供しています。外部連携APIを利用した「オフィスステーション 労務」では、賃金情報・勤怠情報をボタンを押して取り込むだけで、離職票を自動計算して作成してくれます。
労務手続きをミスなくカンタンにする方法を詳しく知りたい方はこちらからダウンロード!
「オフィスステーション労務」の機能や他ソフトとの違いに関する製品カタログをお送りします!
カンタン 30秒で完了
そのほかの関連知識
-

賃金台帳とは? 基礎知識や保管期間、書き方は? ダウンロード用Excelテンプレート付き
-

ペーパーレス会議のメリットや効果は? Web会議ツールの導入やデジタル化の課題・進め方は?
-

労務の内製化に失敗しないための方法とは?
-

バックオフィス業務で残業が発生しやすい要因5つと解決策
-

労働保険料とは?負担者や計算方法、納付時期など押さえるべきポイントを徹底網羅
-

社会保険とは?社会保険料負担の仕組みや負担料、制度の目的などわかりやすく解説
-

e-Govとは?できることや基礎知識、e-Gov電子申請のメリット・デメリットなどまとめ
-

gBizID(GビズID)とは? できることやe-Govとの違いなどを解説
-

雇用契約書とは?作成義務や方法、内容が無効、違法になるケースなどを解説【テンプレートあり】
-

3分で読める! パワハラ防止法の概要と具体策