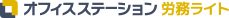お役立ち情報
労働保険とは?基礎知識や企業担当者がおこなうべき手続きまとめ
社労士の声から生まれたソフトだから使いやすい。オフィスステーション 労務で
入退社手続きや有期雇用の更新手続きなどの様々な労務手続きを効率化!
⇒【公式】https://www.officestation.jp/roumu/にアクセスして製品カタログを無料ダウンロード
こんにちは。人事労務クラウドソフト「オフィスステーション 労務」のお役立ち情報 編集部です。
労働者を一人でも雇用する事業者には労働保険の加入義務が発生します。労働保険の目的や仕組み、主な手続きが発生するタイミングや支払者、電子申請で手続きをおこなう方法などまとめました。
- 労働保険とは何か?基礎知識まとめ
- 労働保険料の支払者と給与計算業務時の扱い
- 企業の人事・労務担当者がおこなう労働保険手続き一覧
- 電子申請でおこなえる労働保険手続き
目次
労働保険とは何か? 目的など基礎知識まとめ
労働保険は国が運営する社会保険制度の一つであり、「労働者の保護および雇用の安定を図ること」を目的としています。
また、「労働保険」という言葉は、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」の総称となっています。労働保険の保険給付は2つの制度で別個におこなわれていますが、保険料の納付は「労働保険料」として一体的に扱われます。
労働保険の保険者・加入者・被保険者は誰か?
労働保険の保険者は政府、保険加入者は労働者を雇用する事業所、被保険者は労働者です。企業は加入者にあたるため、労働者を一人でも雇用した場合には、加入の手続きが必要です。
労働保険の保険者
労働保険の保険者は政府であり、その事務をおこなう機関は、中央では厚生労働省、地方では各都道府県の労働局と労働基準監督署となっています。
労働保険の保険加入者
労働者を一人でも雇っている事業場には、その労働者が正社員・パートタイム・アルバイトなどにかかわらず、労働保険の加入が義務づけられています。労働保険の加入者は事業主ですが、事業主代理人を選任することが可能なほか、労働保険事務組合に加入し事務処理を委託することもできます。
労働保険の被保険者
ここでいう労働者は、正社員、パート、アルバイトなど名称や雇用形態に関係なく、労働に対して給与が支払われる従業員のことをいいます。ただし、雇用保険については、一定の条件を満たさない短時間労働者は対象とならないことがあります。
参考:労働保険とは|労働保険特設サイト|厚生労働省
労働保険事務組合制度
労働保険料は誰が支払うのか?
労働保険料の支払者は、労災保険と雇用保険で異なります。このため企業の労務担当は給与計算業務において、それぞれ異なる扱いが必要です。
労災保険料の負担者
労災保険料は、その全額を会社が負担します。給与計算上、従業員の給与や賞与から保険料を控除することはないので、給与計算での処理はありません。
雇用保険料の負担者
雇用保険料は企業と従業員の双方が負担するため、月次の給与計算で控除しなくてはなりません。雇用保険料は毎月の総支給額に料率を乗じて計算するため、月によって雇用保険料額が異なります。
労働保険に関して企業がおこなう手続きとは?
労働保険に関する手続きは、保険加入者・被保険者の情報に変更があったときや、給付金が支給されるタイミングなどで発生します。具体的には以下のような手続きがあります。
| 手続が必要になるタイミング | 提出する書類 |
|---|---|
| 従業員が入社したとき | 雇用保険被保険者資格取得届 |
| 従業員が退職したとき | 雇用保険被保険者資格喪失届 |
| 毎年定期的に行う手続き | 概算・確定保険料申告書 |
| 育児休業、介護休業、60歳到達時 | 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 雇用保険育児休業給付受給資格確認票 介護休業給付金支給申請書 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 雇用継続給付支給申請書 |
| 会社に関する届出、手続き | 保険関係成立届 継続事業一括認可申請書 事業所非該当承認申請書 一括有期事業報告書 名称、所在地等変更届 事業主事業所各種変更届 適用事業所廃止届 労働保険料還付請求書 |
| 業務上の事故・災害があったとき | 療養保障給付たる療養の給付請求書 休業補償給付支給請求書 障害補償給付支給請求書 介護保障給付支給請求書 遺族補償年金支給請求書 遺族補償一時金支給請求書 葬祭料請求書 |
このうち、企業がよくおこなう手続きに、「加入するとき」「従業員が入社したとき」「年度更新」が挙げられます。
労働保険に加入するとき
労働保険は「事業」を単位として成立します。企業そのものが単位ではないので、企業に工場・事務所・支店などが存在する場合は、原則としてその工場・事務所・支店ごとに保険関係が成立します。このため企業が労働保険の適用を受けるようになる場合のほか、企業が支店等を設置した場合にも、「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」の提出が必要です。
まず、「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署または公共職業安定所に提出します。その後、「概算保険料申告書」を労働基準監督署や労働局・日本銀行などに提出し、その年度分の労働保険料を納付します。なお、「保険関係成立届」は労働基準監督署やハローワークの窓口でもらうか郵送してもらう必要があります。
また、事業場が雇用保険の適用事業となったときには「雇用保険適用事業所設置届」および「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所に提出します。
なお、「雇用保険適用事業所設置届」は以下からダウンロード可能です。
雇用保険適用事業所設置届

雇用保険被保険者資格取得届は以下からダウンロード可能です。
雇用保険被保険者資格取得届

従業員が入退社したとき
従業員が入社したときには、「雇用保険被保険者資格取得届」を入社日の翌月10日までに所轄の公安職業安定書に提出します。加入条件は「31日以上雇用される見込みがあり、所定労働時間が週20時間以上」となっています。また、社員が退職したときには「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します。
労災保険については、手続きや届出は不要です。
年度更新
労働保険料は、年に1回「年度更新」と呼ばれる手続きで支払いをおこないます。年度更新は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を期間とし、その年の保険料を概算で申告・納付すると同時に、「前年度に概算で申告した概算保険料」と「実際に支払った賃金から計算した確定保険料」の差額の清算をおこないます。
年度更新の仕組みは以下のとおり。

具体的には、毎年5月頃に労働局から労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率などが印字された申告書が会社に届くため、同封された「賃⾦集計表」を使って賃金総額を求め、それをもとに作成した申告書を、保険料を添えて労働局・労働基準監督署・金融機関などに提出します。

参考:厚生労働省 労働保険の成立手続
【社労士監修】労務手続きのすべてが分かるかんたんガイド
労働保険番号とその調べ方
手続きをおこなう際に労働保険番号が必要になることがあります。
労働保険番号とは?
事業場が労働保険に加入すると、必ず14桁の労働保険番号が付与されます。労働保険番号の桁の意味は以下のとおり。
| 1 府県 | 2 所掌 | 3 管轄 | 4 基幹番号 | 5 枝番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2桁 | 1桁 | 2桁 | 6桁 | 3桁 |
それぞれの意味は以下のようになっています。
-
1.府県
事業所の所在地の属する都道府県 -
2.所掌
労働保険番号の付与が労働基準監督署(1)によるものか、公共職業安定所(3)によるものかを示す番号 -
3.管轄
事務所の所在地を管轄する監督署または安定所を示す番号 -
4.基幹番号
労働保険料の徴収上の事業単位を示す固有番号 -
5.枝番号
特殊な事業の場合、基幹番号に加えて付与される番号
労働保険番号の調べ方
労働保険番号はインターネットで検索できません。労働保険番号は「労働保険関係成立届」の事業主控えに記載されているほか、年度更新の前に労働局から送られてくる申告書にも記載されています。
電子申請でおこなえる労働保険手続き
政府の行政情報ポータル「e-Gov」では、労働保険手続きの電子申請が可能。企業が頻繁におこなう手続きのうち、e-Govで対応しているものの一例は以下のとおり。
| 手続きの区分 | 主な申請契機 | 手続き名 |
|---|---|---|
| 雇用保険被保険者に関する手続き | 従業員が入社したとき 従業員が退社したとき |
雇用保険被保険者資格取得届 雇用保険被保険者資格喪失届 (離職票交付あり) |
| 保険料算定に関する手続き | 賞与支給や定時決定のとき | 健康保険・厚生年金保険に関する手続 |
| 労働保険年度更新に関する手続き | 年度更新のとき | 労働保険年度更新申告 |
| 労働保険保険関係成立に関する手続き | 保険関係成立のとき | 労働保険保険関係成立届 労働保険概算保険料申告 |
e-Govを使って電子申請をおこなうことのメリットは、以下の3つが挙げられます。
- 1.24時間365日、いつでも申請できる
- 2.窓口に出向く交通費や、書類を郵送する費用が不要
- 3.入力の手間が省ける
ただし、e-Govには「入力がしづらい」「進捗を把握しにくい」「電子申請に対応していないものがある」「差し戻しが起こったときに不備が何かを自分で見つける必要がある」「エラーが多い」といった声も聞こえてきます。
労働保険まとめ
労働保険関係の手続きは、企業が運営をおこなう中で切り離すことができません。一方で、リソースの限られる人事・労務担当者にとって、単純作業である手続き業務に割く時間はできる限り短縮したいものです。
e-Govで電子申請することにより窓口に出向く時間は省けます。しかし、企業が利用しているシステムやExcelファイルのデータとの連携がスムーズでないために転記・チェック・修正といった手間が発生することもあります。
従業員の情報を一元化するクラウドサービス「オフィスステーション 労務」は、e-Govの「外部連携API」と呼ばれるツールを使うことで、e-Govの機能をより使いやすくしています。会社が登録している社員情報をもとにボタン一つで申請が可能になり、修正必要箇所も示してくれるほか、戻ってきた公文書をクラウド保存することも可能。人事・労務担当者の手間と時間を大きく削減できるようになっています。
労務手続きをミスなくカンタンにする方法を詳しく知りたい方はこちらからダウンロード!
「オフィスステーション労務」の機能や他ソフトとの違いに関する製品カタログをお送りします!
カンタン 30秒で完了
そのほかの関連知識
-

賃金台帳とは? 基礎知識や保管期間、書き方は? ダウンロード用Excelテンプレート付き
-

【社労士監修】労災(労働災害)隠しはなぜばれる? 企業担当者が労災トラブルを起こさないためにすべきこと
-

労務管理とは? 必要な基礎知識や労務管理がずさんにならないようにするための方法
-

労働保険とは?基礎知識や企業担当者がおこなうべき手続きまとめ
-

ペーパーレス化とは? 目的やメリット・デメリット、方法・進め方、具体的な事例
-

離職票とは?離職証明書・退職証明書との違いや書き方など手続き方法まとめ
-

gBizID(GビズID)とは? できることやe-Govとの違いなどを解説
-

社会保険の扶養条件とは? 対象者の年収額や年金受給者の扱いなどをわかりやすく解説
-

社会保険とは?社会保険料負担の仕組みや負担料、制度の目的などわかりやすく解説
-

36協定とは? 締結・届出の方法や、届け出ないことでのリスクなど徹底解説