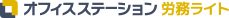お役立ち情報
3分で読める! パワハラ防止法の概要と具体策
社労士の声から生まれたソフトだから使いやすい。オフィスステーション 労務で
入退社手続きや有期雇用の更新手続きなどの様々な労務手続きを効率化!
⇒【公式】https://www.officestation.jp/roumu/にアクセスして製品カタログを無料ダウンロード
こんにちは。人事労務クラウドソフト「オフィスステーション 労務」のお役立ち情報 編集部です。
2022年4月より、中小事業主でも義務化されるパワハラ防止法。どのようなガイドラインに沿って、対策を講じていけばよいのかまとめました。
近年社会問題にもなりつつあるパワーハラスメント(以下、パワハラ)。企業としても、職場秩序の乱れや業務への支障、企業としての社会価値損失にも発展するため、見過ごすわけにはいきません。
こうしたパワハラ問題に対して、厚生労働省では2020年6月より「労働施策総合推進法」、通称パワハラ防止法を施行しました。当初は大企業のみが義務化の対象でしたが、
2022年4月からは中小事業主もパワハラ防止法に基づく防止措置が義務化の対象となります。
パワハラについてはどんなものか理解はしつつも、パワハラ防止法に則ったとき、どのような行為が該当するのか、また中小事業主としてどんな対策を講じるべきなのか、まだまだ分からない方も多いかもしれません。
本記事では、パワハラ防止法の概要や職場におけるパワハラのガイドライン。そして企業として取るべき対策について説明していきます。
- パワハラ防止法の全体像
- 職場におけるパワハラの定義
- パワハラ防止法における具体策
- パワハラ防止法は2022年4月から中小事業主でも義務化される
- 対策は“できればおこなうこと”ではなく“必ずおこなうこと”である
目次
パワハラ防止法とは一体なに?
パワハラ防止法は、正式名称を「労働施策総合推進法」といい、パワハラの基準を法律で定めることで、企業に具体的な防止措置を課す法律です。2022年4月から中小事業主も該当となるため、多くの企業で防止措置のための準備が必要となります。
中小事業主の定義
では、該当の事業主がおこなわなければいけない施策にはどのようなものがあるのでしょうか。詳しくは後述しますが、パワハラ防止法では以下の3項目を必ず講じなければいけないとされています。
- 事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
- 苦情などに対する相談体制の整備
- 被害を受けた労働者へのケアや再発防止
【出典】女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月5日公布)の概要(P.3)-厚生労働省
また3つの項目とあわせて、「講ずべき措置があれば適切におこなうこと」が義務づけられています。例えば、パワハラを受けた側やする側のプライバシーを保護するために必要な措置を取ること。相談したことを理由に解雇や不利益な扱いをされない旨を定め、労働者に周知、啓発することなどが該当します。
意外と知らない、パワハラのガイドライン
パワハラ防止法の全体概要について、まずは簡単にまとめましたが、「パワハラ」と一言で表現しても、その解釈は人によってバラバラです。厚生労働省が定義する「職場におけるパワーハラスメント」について、明確なガイドラインを示しつつ、より分かりやすく説明していきます。
「職場におけるパワーハラスメント」の定義とは、厚生労働省によると以下3つの要件をすべて満たすものを指します。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
それぞれ、具体例を交えながら解説します。
「1.優越的な関係性を背景とした言動」とは、業務を遂行するにあたり、パワハラを受ける側とする側に、抵抗・拒絶することができない関係性が背景にあるかということです。
代表的なのは、上司と部下といった、職務上の地位の上下を背景とした言動です。また同僚同士の関係でも、業務を教える、教わるといった関係性の上で言動があった場合も、優越的な関係性があるものと解釈できます。
また、同僚や部下からの集団による行為によって、抵抗や拒否ができないという場合も、
「1.優越的な関係性を背景とした言動」に該当します。
「2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」の定義は、社会通念に照らし合わせて、その言動が明らかに業務上必要性のないものを指します。
例えば、注意やアドバイスの範疇を超えて個人の人格を否定するような言動をしたり、相手に暴力を振るったり、長時間にわたって精神的に苦痛を伴う激しい叱責をするなどがこれに当たります。
「3.労働者の就業環境が害されるもの」とは、パワハラする側の言動により、労働者が身体的又は精神的に苦痛を感じ、就業環境が不快なものとなったために能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、見過ごせない程度の支障が生じることを指します。
この場合、言動や行為の頻度などは考慮されるものの、強い身体的及び精神的苦痛を伴う言動の場合には、行為が1回だけでも就業環境を害する場合があると解釈されます。
1つ1つの事案は、この3つの要件に当てはめるだけでなく、言動の目的やおこなわれた状況など総合的に考慮し、判断していきます。
またパワハラに該当すると考えられる具体例について、厚生労働省のWebサイトにも細かく記載がありますので参考にしてみてください。
厚生労働省Webサイト職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
パワハラ防止法の具体策を紹介
ここからは、事業主がパワハラを防止するため、具体的にどのような措置を講ずべきか、詳しくご紹介していきます。
記事の冒頭で、パワハラ防止法では以下の3つの項目を必ず講じなければいけないと説明しました。では、実際どのような対策をとっていけばよいのかご説明します。
- 事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
- 苦情などに対する相談体制の整備
- 被害を受けた労働者へのケアや再発防止
1.事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
パワハラの内容や定義、おこなってはならない旨の方針を明確化し、監督者や労働者に正しく周知・啓発をしていきます。また、パワハラをした側には、厳正に対処する旨の方針、対処内容も同じく明確化して周知・啓発していきます。
具体的には、就業規則にパワハラについて具体的な定義や対処内容を明記し、従業員に周知していくこと。社内報や社内Webサイト等に、啓発のための資料を閲覧できるようにする。ハラスメントの内容や発生原因、背景についての事業主としての方針を記載し配付するなどがあげられます。
2.苦情などに対する相談体制の整備
相談窓口をあらかじめ設置し、労働者に周知すること。また、相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすることが該当します。これと合わせて、パワハラが発生するおそれがある場合や、該当するか否か微妙な場面でも、広く相談に応じられるような窓口であることが重要です。
3.被害を受けた労働者へのケアや再発防止
事実関係を迅速かつ正確に確認すること。また確認にあたり、被害者に対する配慮措置を適正におこなうこと。確認後は、パワハラをおこなった側に対して、適正な措置をおこなうこと。また、事実確認ができなかった場合でも再発防止に向けた措置を講ずる必要があります。
これと合わせて、事業主として、双方のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、また相談したことで被害者側が解雇や不利益な扱いをされないような旨を定め、周知・啓発していくことも大切です。
まとめ
ここまでパワハラ防止法の全体概要や、講ずべき具体的な措置についてご紹介してきました。具体的な対応と合わせて、パワハラ防止法に詳しい社会保険労務士に自社の課題を相談したり、管理職にパワハラ防止を目的とした各種講習を受けさせたりするといった準備をしている企業もあるようです。
労務手続きをミスなくカンタンにする方法を詳しく知りたい方はこちらからダウンロード!
「オフィスステーション労務」の機能や他ソフトとの違いに関する製品カタログをお送りします!
カンタン 30秒で完了
そのほかの関連知識
-

離職票とは?離職証明書・退職証明書との違いや書き方など手続き方法まとめ
-

3分で読める! パワハラ防止法の概要と具体策
-

賃金台帳とは? 基礎知識や保管期間、書き方は? ダウンロード用Excelテンプレート付き
-

雇用契約書とは?作成義務や方法、内容が無効、違法になるケースなどを解説【テンプレートあり】
-

バックオフィス業務で残業が発生しやすい要因5つと解決策
-

労働保険料とは?負担者や計算方法、納付時期など押さえるべきポイントを徹底網羅
-

e-Govとは?できることや基礎知識、e-Gov電子申請のメリット・デメリットなどまとめ
-

労働保険とは?基礎知識や企業担当者がおこなうべき手続きまとめ
-

労務管理とは? 必要な基礎知識や労務管理がずさんにならないようにするための方法
-

労災保険の休業給付を受けるには? 要件や計算方法を誰でもわかるように解説