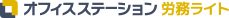お役立ち情報
労災保険の休業給付を受けるには? 要件や計算方法を誰でもわかるように解説
社労士の声から生まれたソフトだから使いやすい。オフィスステーション 労務で
入退社手続きや有期雇用の更新手続きなどの様々な労務手続きを効率化!
⇒【公式】https://www.officestation.jp/roumu/にアクセスして製品カタログを無料ダウンロード
こんにちは。人事労務クラウドソフト「オフィスステーション 労務」のお役立ち情報 編集部です。
労災保険とは、正式名称を「労働者災害補償保険」といい、私たちが業務中や通勤時の災害によるケガや、業務が原因で病気になり仕事がまったくできなくなったときに、治療費や休業補償などをおこなう保険です。労災保険の適用や補償にはいくつかありますが、今回は「休業補償給付」について解説していきます。
- 休業補償給付の請求対象と条件
- 休業補償給付額の計算方法
- 休業補償給付の請求方法
- 早く給付できるための「受任者払い制度」活用方法
- ただ労働中にケガをしたり、病気になったりしただけでは適用されない場合がある
- 1日あたりの休業補償給付は給付基礎日額の80%
目次
休業補償給付とは? 支給に必要な3つの要件
休業補償給付とは、前述したように業務中または通勤時の災害によるケガや、業務が原因で病気になることで仕事がまったくできなくなったときに、支給されるものです。
休業4日目から支給されるものですが、給付基礎日額に対し、休業補償給付として60%、休業特別支給金として20%の合計80%分が支給されます。
休業補償給付を請求するためには、ただ労働中にケガをしたり、病気になったりしただけでは適用されない場合があります。以下3つの要件をすべて満たしていることで、休業補償給付の請求が可能になります。
1 業務上の事由による負傷や疾病による療養をしていること
2 上記1の療養のため、労働することができない状態であること
3 労働することができないため、賃金の支給を会社から受けてないこと
この3つの要件をすべて満たすことで、休業4日目から休業補償給付(60%)、および休業特別支給金(20%)が支給されます。
休業特別支給金とは
労災保険の各給付金に上乗せして支払われる特別支給金の一種です。
特別支給金には以下9種類がありますが、休業補償給付に上乗せして支払われるのは休業特別支給金です。特別支給金の支給額は、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額となり、休業補償給付の60%と合わせると、労働者に合計80%の給付がされるようになっています。
- 休業特別支給金
- 障害特別支給金
- 障害特別年金
- 障害特別一時金
- 遺族特別支給金
-
遺族特別年金
- 傷病特別支給金
- 遺族特別一時金
- 傷病特別年金労働者
また、休業初日から3日目までを「待期期間」と呼び、休業補償給付金が給付されません。そのかわり、待期期間中は会社(事業主)が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%、ただし100%補償する会社が多い)をおこないます。
このとき大事なのは、賃金として支給を受けるのではなく、補償金として支給を受けることです。また、該当社員は有休などを使わず、会社からきちんと休業補償を受けるようにすることが大切です。
労災保険の休業補償給付の対象は「すべての労働者」が対象
労災保険の給付制度では「すべての労働者」が補償対象です。雇用形態や勤務日数・時間などに関係せず、正社員やパート、アルバイト、日雇い労働者や季節雇用など直接契約をおこなうすべての労働者が対象です。
ただし、以下は直接契約をしている労働者とは呼ばず、対象外となります。
派遣社員
派遣社員の場合、働く会社と直接契約をしていないため対象外となります。労災保険は派遣元の事務所が加入します。
事業主や役員
労災保険は労働者を守るための制度です。そのため、会社の代表や役員は労災保険の対象にはなりません。ただし、「取締役」などの役職でも、労働者と同条件で働き対価を得ている場合は対象となります。
一人親方や個人事業主
自営業者は労働者ではありませんので、労災保険の対象にはなりません。また業務委託契約で仕事をしている場合にも、労災の給付対象にはなりません。
また、近年複数の会社に雇用されるケースも増えていますが、2020年9月1日に労働者災害補償保険法が改正され、給付の対象が変わりました。
以前は、事故が起きた勤務先の賃金額のみを基礎に、給付額が決定していました。改正後は、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に、給付額等が決定することになりました。疾患などにかかった場合も、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して、労災認定されるようになりました。併せて覚えておくと安心です。
【参考】労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~│厚生労働省
支給額は給付基礎日額と休業日数が基準
ここからは、ご自身が休業補償給付と特別支給金を合計いくらもらえるか、具体的な計算方法について解説していきます。
さきほども簡単に触れましたが、労働中にケガや病気になり休業をした場合、会社からは休業補償給付として給付基礎日額の60%、休業特別支給金として給付基礎日額の20%、合わせて給付基礎日額の80%が支給されます。
給付基礎日額の計算方法
給付基礎日額は、原則として労働基準法における平均賃金に相当する額を指します。具体的な算出方法は、事故が起きた日や疾病が確定した日(医師の診断結果が出た日)の直前3カ月間において、労働者に対して支払われた賃金の総額を、日数によって割った金額が給付基礎日額となります。
賃金総額には残業手当などは含みますが、ボーナスや結婚手当のように臨時的に発生した賃金は考慮されませんので、注意しましょう。
これらを踏まえて、例えば月20万円の賃金を受け取っていた労働者が、10月にケガをして休業した場合の各種金額を計算してみましょう。
20万円×3カ月÷92日(7月は31日+8月は31日+9月は30日)=6,522円(1円以下の端数切り上げ)
6,522円×60%=3,913円(1円以下端数切捨て)
6,522円×20%=1,304円(1円以下端数切捨て)
3,913円+1,304円=5,217円
この金額に、支給対象期間の日数をかけていけば、休業補償給付としていくらもらえるかが分かります。休業期間は仕事ができず、不安が募る方もいるかもしれません。賃金の80%が給付されるのであれば、生活の面での不安もある程度払拭し、治療に専念することができるでしょう。
労災保険の請求書類と提出先について
休業補償給付と休業特別支給金を受け取るには、労働者本人が所轄労働基準監督署へ書類を提出しなければなりません。
請求に必要な書類は、休業給付の場合以下の2点です。
- 休業補償給付支給請求書(8号)
- 休業給付支給請求書(16号の6)
これらの書類は、厚生労働省のWebサイトからダウンロードが可能です。
また、会社(事業主)側は、「労働者のケガや疾病が労働中に起こった」という証明をおこない、後のトラブルにならないためにもきちんと対応しましょう。合わせて、休業期間が長期にわたる場合は、1カ月ごとの提出が必要になりますので、その点も従業員に伝えておきましょう。
書き方や今回紹介した休業補償給付に関する詳細について、厚生労働省のWebサイトより「休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続」を参考にすると、より理解が深まります。
【参考】休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続│厚生労働省
「受任者払い制度」を活用し、給付を早める!
ここまで、労災保険の休業補償給付について説明してきました。
休業補償給付を受けるには、労働者からの請求や労働基準監督署での審査を通る必要があり、実際の支給は請求から1カ月以上先であることが多いようです。そのため、実際の支給までは相当の時間を要するとされています。
こうした給付を待つ間に労働者の生活が立ちいかなくなることを回避するため、「受任者払い制度」を活用することで、不利益や生活不安を回避することができます。
受任者払い制度とは、従業員が労災保険から受け取る給付金を、会社が従業員に立替払いをする制度です。この制度を利用した場合、労災認定後に支給される休業補償給付金は、立て替え払いをした会社の口座に振り込まれるようになります。
この制度を活用することで、被災労働者は受け取る予定の給付金と同額を早期に支払ってもらうことができ、治療や生活の安定に当てることができます。注意点として覚えておきたいのが、万が一労災として認定されなかった場合、会社から支払われた立替金は返還しなくてはならないということです。
受任者払い制度を利用する場合は、以下の書類を提出します。
なお、都道府県によって申請書類の書式が異なりますので、管轄する労働基準監督署に問い合わせておきましょう。
- 給付を受ける労働者の委任状
- 受任者払いに関する届出書
これと合わせて、先程記載した「休業補償給付支給請求書(8号)」「休業給付支給請求書(16号の6)」も必要になります。合わせて準備し提出します。
まとめ
労働者を1人でも雇用している場合には、加入が義務付けられている労災保険。また保険料は全額事務所が担わなくてはなりません。
中小企業にとっては大きな出費となるかもしれませんが、労働災害が発生した場合、会社として負わなければならない責任や負担はそれ以上です。また近年は「労災隠し」などの問題もたびたびニュースなどで取り上げられています。労働災害が発生した場合、所轄の労働基準監督署への報告が義務付けられており、隠蔽や虚偽の報告をした場合、刑事責任の対象となるケースもあります。こうしたことがないように必ず適切な環境整備はおこなっていきましょう。
労働者が気持ちよく仕事に取り組めるよう、会社として安心できる環境を提供するため、制度を整え、準備・確認をしておくことは大切です。
労務手続きをミスなくカンタンにする方法を詳しく知りたい方はこちらからダウンロード!
「オフィスステーション労務」の機能や他ソフトとの違いに関する製品カタログをお送りします!
カンタン 30秒で完了
そのほかの関連知識
-

労務管理とは? 必要な基礎知識や労務管理がずさんにならないようにするための方法
-

【社労士監修】労災(労働災害)隠しはなぜばれる? 企業担当者が労災トラブルを起こさないためにすべきこと
-

36協定とは? 締結・届出の方法や、届け出ないことでのリスクなど徹底解説
-

労務の内製化に失敗しないための方法とは?
-

労働保険とは?基礎知識や企業担当者がおこなうべき手続きまとめ
-

労働保険料とは?負担者や計算方法、納付時期など押さえるべきポイントを徹底網羅
-

e-Govとは?できることや基礎知識、e-Gov電子申請のメリット・デメリットなどまとめ
-

gBizID(GビズID)とは? できることやe-Govとの違いなどを解説
-

社会保険の扶養条件とは? 対象者の年収額や年金受給者の扱いなどをわかりやすく解説
-

賃金台帳とは? 基礎知識や保管期間、書き方は? ダウンロード用Excelテンプレート付き