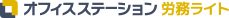お役立ち情報
労務の内製化に失敗しないための方法とは?
社労士の声から生まれたソフトだから使いやすい。オフィスステーション 労務で
入退社手続きや有期雇用の更新手続きなどの様々な労務手続きを効率化!
⇒【公式】https://www.officestation.jp/roumu/にアクセスして製品カタログを無料ダウンロード
こんにちは。人事労務クラウドソフト「オフィスステーション 労務」のお役立ち情報 編集部です。
アウトソーシング、つまり企業が外部に業務を委託すると、社内にノウハウがなくても専門性の高い業務をおこなうことができ季節的な業務量の変動にも対応できますが 、その分だけ費用がかかります。
【参照元】アウトソーシング活用の効果 人事・労務の業務について社労士や代行業者にアウトソーシングをおこなっている企業も多く存在しますが、費用が大きな負担となっている場合は、内製(インソーシング)することでコスト削減を図ることが可能です。労務の内製化を検討する上で知っておくべきメリット・デメリットや、内製化でDXする方法、内製化に失敗しないためにはどうすればいいのか、逆にアウトソーシングが効果的な場合などについてまとめました。
- 労務の内製化をおこなうことのメリットとデメリット
- 内製化できる具体的な業務と内製化する上でのポイント
- 労務の内製化に失敗するケース
- 労務の業務を内製化することで、コスト削減だけではなく、アウトソーシングにかかっている作業量や作業時間を減らすことも可能
- 業務を「定型的な業務」と「非定型的な業務」に大別し、前者をシステム的に、後者を人間の力で解決していくことで効率化が図れる
目次
労務の内製化のメリットとデメリットは?
労務の内製化をおこなうことのメリットとデメリットは以下のとおりです。

労務の内製化のメリット①【社内にノウハウを蓄積できる】
アウトソーシングをおこなうと業務の目的を達成することはできますが、途中経過のプロセスを把握することはできません。このため業務がブラックボックス化し、効率化や生産性向上を図ることができなくなります。労務の内製化に成功すれば、社内にノウハウを蓄積し、人材を教育し、さらなる生産性向上を目指すことが可能になります。
労務の内製化のメリット②【アウトソーシングよりも作業量が減ることも】
社外に業務を委託する場合でも、委託前にデータの加工が必要なケースが存在します。アウトソーシングの際に担当者が単純な転記やチェックを何度もおこない、誤りを発見した場合はさらにチェックを繰り返す……といった作業時間が多い場合は、適切に内製化することで、作業時間を削減することができます。
労務の内製化のメリット③【意思疎通がスムーズになる】
内製化をおこなうと、労務のやりとりに第三者を挟まないため、全体的な進行スピードがアップします。委託先では対応できないイレギュラーな事態についても、迅速に対応し、トラブルを回避することができます。
労務の内製化のメリット④【情報漏洩のリスクが減る】
アウトソーシングをおこなう場合は、従業員の個人情報や給与計算業務に関する重要な情報を委託先に渡さなければなりません。委託先による情報の取り扱い方によっては、インターネット上に情報が流出したり、悪用されたりといったことも考えられます。内製化は重要な情報を社内にとどめることができるため、情報漏洩のリスクは低くなります。
労務の内製化のデメリット①【業務が属人化しやすい】
給与計算や社会保険手続きは、専門的な知識を要します。知識を有する特定の人物しか業務を進められない状態では、その人物が休職・退職などしたときに業務がストップしてしまうというリスクがあります。
労務の内製化のデメリット②【担当者の負担が増加する】
内製化するために、すでに存在する従業員に作業を割り振ると、 その分、従業員の負担は増加します。また、重要な情報を扱っていることから、情報管理の心理的負担が増すことも考えられます。
労務の内製化のデメリット③【人件費や設備投資の費用が必要】
少人数の担当者で業務にあたる場合、特に担当者の経験が浅いと、残業が増加する傾向にあります。繁忙期には残業が増加したり、一時的に人員を増加させることも考えなければなりません。また、人件費以外にも、PCやシステムなどの設備の導入費用や維持費がかかります。
労務の内製化のデメリット④【人材の育成に時間がかかる】
労務の業務範囲は広いため、専門知識を有する人材を育成するためには日常業務の範囲を超えた教育や研修が必要です。育成する人材を選定し、教育のためのチームを構成し、実際に教育していく……、というプロセスには長期的な視点を要します。
内製化の2つの方法
労務の内製化を進める方法は主に以下の2つがあります。
- 労務に担当者を置く方法
- 業務効率化ツールを使う方法
内製化の方法①【労務に担当者を置く方法】
労務の専門知識を有する担当者を置くと、給与計算・年末調整・社会保障手続きといった日常的な業務がスムーズにおこなえるだけでなく、法改正に対応した就業規則・社内ルールや福利厚生制度企画、従業員トラブルの回避など、強い組織を作るために重要な施策を充実させることができます。一方で、業務量に対して人的リソースが不十分な場合は、労務が単純な計算処理業務部門になってしまい、専門知識を生かす生産性の高い業務にまで手が回らず、十分な費用対効果を生み出せない可能性もあります。
内製化の方法②【業務効率化ツールを使う方法】
効率よく労務の業務をおこなうためには、「単純な事務作業や計算処理業務といった定型的な業務」と「人の関わりが必要な非定型的な業務」に分け、前者をコンピューターで効率化していくという発想も重要です。給与計算・年末調整・労務手続きなどは前者にあたり、システムに任せることで速いスピードで正確な結果が得られます。また、これらの作業を専門的な知識なしでおこなえるようになるため、担当者が入れ替わっても混乱が生じにくいというメリットもあります。 定型的な業務をシステム化することで、社内のDX化を進めることもできます。日本では将来的に企業の人材不足が予想されていますが、DX化を進めることでコスト削減を図りながら人材不足に対処し、より優秀な人材を集めることに集中できます。
労務でDX化した事例については以下の記事から確認できます。
労務の内製化の課題
労務の内製化の課題①【給与計算】
給与計算の業務には、以下の2つの目的があります。
- 決められた日時に従業員に正しい金額の賃金を支払う
- 所得税や社会保険料といった国に支払うお金を計算して納付する
2つの目的を遂行するためには、まず勤怠管理を適切におこない、複数の店舗や営業所からタイムカードを期日までに回収して、データを集計する必要があります。また、「時間外・休日・深夜勤務などの割増賃金の取り扱い」「年次有給休暇の取り扱い」に対する賃金を支給するための知識や、社会保険料や所得税の計算をおこなうための法律の知識も必要です。
このため、給与計算の業務を内製化する場合は、「知識のある人が会社に存在するのか?」「いない場合は代わりに給与計算ソフトを導入できるか?」という点が検討すべき課題となります。
労務の内製化の課題②【年末調整】
年末調整は書類の送付、回収からはじまり、期限が過ぎれば電話やメールでの督促、書類に不備があれば差し戻し、従業員からの質問に答え、再度回収……と、工数が膨大になる傾向にあります。年末調整を人的リソースで内製化する場合は「一時期だけ作業をする人員を増やす」という方法になりますが、人員の確保に別途準備が必要であることや、入った人員に教育する時間や手間についても考慮する必要があります。
労務の内製化の課題③【社会保険手続き業務】
社会保険手続き業務は、従業員の入退社や結婚・離婚といったライフイベント、年齢に伴って発生する手続きなど、多岐におよびます。知識や経験がないと、都度内容を調べることになり、時間と手間を要します。また、毎年おこなわれる法改正により手続きが変化していくため、常に情報のアップデートが必要です。 手続きに関して従業員とのやりとりが必要なケースも多いため、内製化の際には、「専門知識がある人が会社に存在するのか?」「いない場合は代わりの労務ソフトやシステムを導入できるのか?」「担当者と従業員のやりとりの手間をどのように減らしていくのか」がポイントとなります。

オフィスステーション 労務ならペーパーレスだから転記などのムダな業務は一切なし
労務の内製化で失敗してしまうケースとは?
労務の内製化の失敗例①【内製化する業務領域を絞り込めていない】
コスト削減を目的に何もかもを内製化してしまうと、逆に従業員の負担が増加したり、仕事の質が落ちたりするリスクが考えられます。まずは内製化で削減できるコストと、増加する負担やコストを可視化し、「増員するための人件費・設備投資よりも削減コストの方が大きい」業務について内製化を考えます。
労務の内製化の失敗例②【「人件費」と「外注費」だけを比較して内製化を決める】
内製化において、今いる人員に労務の業務を割り振る場合、一見するとコスト削減が図れるのですが、マルチタスクによってコア業務が疎かになることが考えられます。このような「生産性の下落」は目に見えづらいもの。単純な人件費と外注費の比較だけでなく、組織全体の生産性に悪影響が出ない方法で内製化を進めることが大切です。
労務の内製化の失敗例③【人材が確保できていない状態で内製化する】
担当者が1人しかいない場合は、急な病欠で企業全体の労務手続きや給与計算、勤怠シメなどがストップしてしまう危険性があります。担当者が少ない場合は専門知識がなくとも業務を進められるようにすべく、「脱属人化」を前提として効率化を進める必要があります。
「オフィスステーション 労務なら入退社手続きを脱属人化&作業時間がわずか19分に短縮できる」
労務のアウトソーシングが効果的な場合と業者の選び方は?
労務のアウトソーシングの効果と業者の選び方①【代行する業務の範囲と目的を決定する】
労務の業務をアウトソーシングする場合は、主に以下の2つの方法が考えられます。
- 特定の業務に特化した代行サービスを利用する
- 社労士事務所に依頼する
いずれの方法を取る場合でも、まずは「何を」「どこまで」「なぜ」アウトソーシングするのかを決めることで、目的に合致した委託先を選ぶことができます。
労務のアウトソーシングの効果と業者の選び方②【システム導入が必要か】
社労士事務所や代行サービスに業務をアウトソーシングする場合、委託先によって使用するシステムが決まっていることがあります。社内で使用するシステムと、委託先のシステムが異なると、かえって業務が煩雑になることが考えられるため、システム導入の際には業務全体の連携方法やフローを把握しましょう。
労務のアウトソーシングの効果と業者の選び方③【セキュリティ】
労務のうち、給与計算では個人情報を扱います。また社会保険手続き業務ではマイナンバーなどの特定個人情報も取り扱います。このため、業務の委託先である企業がセキュリティに関して第三者機関の認証を受けているかどうかや、情報の保管場所として使用しているシステムのセキュリティ強度を確認する必要があります。
労務の内製化のまとめ
労務の内製化を検討するには、まず内製化の目的を明確にすることが大切です。「コスト削減」「ノウハウの蓄積」「セキュリティ向上」「作業時間の削減」など、目的を明確にしたうえで、どのような方法で、どの業務を内製化すれば目的を達成できるのかを検討します。このとき、まずは業務を「定型的業務」と「非定型的な業務」に分け、定型的な業務をコンピューターで、非定型的な業務を人的作業で解決することがポイントになります。
そして、「コンピューターによる業務効率化ツールを使う」「労務に担当者を置く」といった方法で内製した場合に、アウトソーシング時と比べて、状況がどのように変化するかをシミュレーションします。なお、業務そのものだけではなく、全体の連携方法やフローを確認することで、「内製化したことでかえって手間やコストが発生した」という事態を防ぐことができます。
労務手続きをミスなくカンタンにする方法を詳しく知りたい方はこちらからダウンロード!
「オフィスステーション労務」の機能や他ソフトとの違いに関する製品カタログをお送りします!
カンタン 30秒で完了
そのほかの関連知識
-

離職票とは?離職証明書・退職証明書との違いや書き方など手続き方法まとめ
-

社会保険とは?社会保険料負担の仕組みや負担料、制度の目的などわかりやすく解説
-

労務の内製化に失敗しないための方法とは?
-

ペーパーレス会議のメリットや効果は? Web会議ツールの導入やデジタル化の課題・進め方は?
-

労災保険の休業給付を受けるには? 要件や計算方法を誰でもわかるように解説
-

36協定とは? 締結・届出の方法や、届け出ないことでのリスクなど徹底解説
-

雇用契約書とは?作成義務や方法、内容が無効、違法になるケースなどを解説【テンプレートあり】
-

gBizID(GビズID)とは? できることやe-Govとの違いなどを解説
-

社会保険の扶養条件とは? 対象者の年収額や年金受給者の扱いなどをわかりやすく解説
-

e-Govとは?できることや基礎知識、e-Gov電子申請のメリット・デメリットなどまとめ