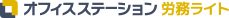お役立ち情報
労務管理とは? 必要な基礎知識や労務管理がずさんにならないようにするための方法
社労士の声から生まれたソフトだから使いやすい。オフィスステーション 労務で
入退社手続きや有期雇用の更新手続きなどの様々な労務手続きを効率化!
⇒【公式】https://www.officestation.jp/roumu/にアクセスして製品カタログを無料ダウンロード
こんにちは。人事労務クラウドソフト「オフィスステーション 労務」のお役立ち情報 編集部です。
従業員を一人でも雇用している場合、企業に求められる「労務管理」。主活動ではないため企業では後回しにされがちですが、ずさんな労務管理には「人材が定着しない」「労働問題が発生して企業イメージが下がる」といったリスクが伴います。企業の将来を左右する重要な要素である「労務管理」の具体的な仕事・業務の内容や、効率化などについて解説します。
- なぜ企業には労務管理が必要?
- 労務管理の基本と業務内容
- ずさんな労務管理がもたらす企業・従業員への危険性
- 企業の生産性を上げるために必要な「効率的な労務管理」のポイント!
目次
労務管理とは?
労務管理業務とは、「企業と従業員の健全な労使関係の維持」をサポートする業務全般を指します。使用者である企業と労働者である従業員の関係は、労働法の定めのもと労働契約・労働協約・就業規則などによって決まります。適切な労務管理をおこなうためには、法律を正しく理解し、就業規則を始めとする制度の整備が求められます。また会社の規模や従業員の人数にかかわらず、従業員が一人でもいる場合には、企業は労務管理をおこなわなければなりません。
労務管理の目的と担当者
労務管理の目的は、従業員の生産性向上と企業の収益性を高めることにあります。この方法として「従業員の働きやすい環境を作ること」「労働トラブルのリスクを下げること」が求められるため、企業のバックオフィスである人事・労務・総務が労務管理を担当することが一般的です。
労務管理業務の具体例
労務管理業務は多岐におよびますが、以下のようなものが一例として挙げられます。
- 就業規則の作成
- 雇用契約書の作成
- 入退社の手続き
- 法定三帳簿の作成・保存
- 社会保険・雇用保険の手続き
- 勤怠管理・給与計算
- 従業員の健康管理(安全衛生管理)
- ハラスメント対策
- 福利厚生
- 労働トラブルにおける対応
労務管理の核となる「法定三帳簿 」とは?
労働基準法では、労働者を雇用した場合に「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3つを整備・管理し、一定期間保存することを義務づけており、違反すると処罰の対象になります。
労働者名簿
労働基準法等を根拠とする従業員の氏名や生年月日などさまざまな情報を記した書類のことであり、労働者名簿には以下の事項を記載する必要があります。
- 労働者氏名住所
- 生年月日
- 履歴
- 性別
- 住所
- 従事する業務の種類
- 雇入年月日
- 退職や死亡年月日、その理由や原因
【保存期間と起算日】
保存期間は3年、起算日は労働者の死亡・退職・解雇の日です。
【様式】
様式第19号(ここから ダウンロードできます)

賃金台帳
賃金計算の基礎となる事項や賃金の額が記載されたもの であり、労働者名簿には以下の事項を記載する必要があります。
- 労働者氏名
- 性別
- 賃金の計算、期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働時間数
- 深夜労働時間数
- 休日労働時間数
- 基本給や手当等の種類と額
- 控除項目と額
【保存期間と起算日】
保存期間は3年、起算日は労働者の最後の賃金について記入した日です。
【様式】
様式20号(常用)、21号(日雇)
(様式20号のダウンロードはここから 、様式21号のダウンロードはここから 可能です)

出勤簿等
従業員の出退勤に関する記録をまとめた帳簿であり、出勤簿等には以下の記載が求められています。
- 出勤簿やタイムレコーダー等の記録
- 使用者が自ら始業・終業時刻を記録した書類
- 残業命令書およびその報告書
- 労働者が記録した労働時間報告書等
【保存期間と起算日】
保存期間は3年、起算日は労働者の最後の出勤日です。
【様式】
様式は任意です。

近年は不正アクセスやサイバー攻撃が活発化しており、重要な個人情報が記載される法定三帳簿が攻撃の対象になることもあります。実際に、2021年にも東証一部上場企業が不正アクセスを受けて人事情報が流出しました。「業務効率化」と「セキュリティ」という両方の観点から、法定三帳簿は電子化ツールによる業務改善が求められる部分です。
ずさんな労務管理にともなう企業と従業員へのリスク
帳簿の作成や保存だけでなく、就業規則や雇用契約の整備も労務管理の重要な業務です。これらが不十分な場合、労働関係の悪化やトラブルが起こりやすくなります。実際に、労務管理が不十分であったことから多くの事件が発生し、企業や従業員に損害が生じています。
ずさんな労務管理の例1. 残業代未払い問題
大手小売りチェーンでアルバイトやパート従業員の残業手当の一部が支払われていなかったことが2019年に判明しました。未払いとなっている残業代は約5億円にものぼりますが、原因は労働時間と残業代の計算方法の誤りだとされています。
ずさんな労働管理の例2. 違法残業事件
2017年に発覚した違法残業事件で、法定労働時間を超えて従業員を働かせるために必要な「36(サブロク)協定」が無効だったことが判明しました。労働基準法36条では「事業場の過半数で組織する労働組合または過半数を代表する者」が協定を結ぶ必要があるとしていますが、締結当時、労働組合の加入者は従業員の半数以下でした。
ずさんな労働管理の例3. パワハラ事件
2019年に大手総合電機メーカーの従業員が自殺した一件が、2021年に労働者災害認定されました。同社ではほかにも自殺した従業員の労働者災害認定が相次ぎ、社長ら役員が処分されています。
ずさんな労務管理は企業の評価を大きく下げます。悪いイメージや評価がついた企業には優秀な人材が集まらず、また労働環境が悪化することで従業員の健康が損なわれたり、定着率が下がったりと、生産性低下の大きな原因となります。
日本の労働人口は今後15年で1,000万人減少するといわれています。将来的な人材確保が困難になる状況のなか、適切な労務管理をおこなうことが企業の競争力を上げるためには不可欠です。
労務管理を効率化して従業員の生産性を上げるには?
従業員の生産性を上げるためには、就業規則や福利厚生の見直しによって「従業員が働きやすい環境」を作ることが必要ですが、これは一朝一夕でおこなうことはできません。労務管理で企業の生産性を上げるためには、「時間をかける部分」と「効率化する部分」を明確にし、効率化によって時間を生み出す必要があります。

リソースが少ないバックオフィスが労働環境を整えるためにはまず、定型業務を効率的におこなうための仕組み作りやシステム導入について考えていくことが重要です。
労務管理における業務改善ポイント!
- 課題を明確にする
- 専門家との連携、業務のアウトソーシングを検討する
- 労務ソフトウェアやツールの見直し
1.企業の課題を明確にする
労働環境を改善するためには、まず現状の問題を洗い出す必要があります。「有休消化率が低い」「従業員の定着率が低い」「時間外労働が多い」「ハラスメントの訴えがある」など、解決すべき問題を洗い出し、それぞれの問題への解決方法を考えます。
2.専門家との連携、業務のアウトソーシングを検討する
企業と労働者の関係を円滑にする労務管理には、労使問題の解決が含まれます。ハラスメント対応を含め労務管理には法律の知識が必要であるため、人事・労務・総務に専門知識を持つ担当者がいない場合は、社労士事務所などに業務をアウトソーシングすることも方法として考えられます。
3.労務ソフトウェアやツールの見直し
勤怠管理・給与計算・労務手続きといった定型的で単純な作業がメインとなるタスクは、コンピューターに任せた方が速く正確です。しかし、ソフトウェアやツールを使っていても連携がうまくいっていなかったり、紙での作業が残っていたりすると、作業工数や作業時間が膨らむこともあります。この場合、ソフトウェアやツール同士の連携をスムーズにし、転記やチェック作業を減らすといった「業務フローの改善」を目的とした見直しが必要です。
労務管理のまとめ
日本の労務管理は歴史的に終身雇用・年功制でしたが、近年は労働環境が大きく変化しています。雇用形態の多様化・労働時間の短縮・テレワークの導入などが労務の課題として挙げられますが、これらは経営に直結するため「どのような組織を作っていくべきか」を前提に慎重に検討する必要があります。限られたリソースの中で重要な労務の課題を解決するため、定型的で時間のかかる手続きはシステムの導入など、自動化・効率化ツールを使ってできる限り効率化することが「少数精鋭の人事・労務」の鍵といえます。
システム同士の連携をスムーズにして、労務手続きにかかる時間を93%削減できる「オフィスステーション 労務」の詳細は以下から確認することが可能です。
労務手続きをミスなくカンタンにする方法を詳しく知りたい方はこちらからダウンロード!
「オフィスステーション労務」の機能や他ソフトとの違いに関する製品カタログをお送りします!
カンタン 30秒で完了
そのほかの関連知識
-

ペーパーレス化とは? 目的やメリット・デメリット、方法・進め方、具体的な事例
-

労災保険の休業給付を受けるには? 要件や計算方法を誰でもわかるように解説
-

離職票とは?離職証明書・退職証明書との違いや書き方など手続き方法まとめ
-

賃金台帳とは? 基礎知識や保管期間、書き方は? ダウンロード用Excelテンプレート付き
-

労働保険料とは?負担者や計算方法、納付時期など押さえるべきポイントを徹底網羅
-

社会保険の扶養条件とは? 対象者の年収額や年金受給者の扱いなどをわかりやすく解説
-

雇用契約書とは?作成義務や方法、内容が無効、違法になるケースなどを解説【テンプレートあり】
-

【社労士監修】労災(労働災害)隠しはなぜばれる? 企業担当者が労災トラブルを起こさないためにすべきこと
-

3分で読める! パワハラ防止法の概要と具体策
-

バックオフィス業務で残業が発生しやすい要因5つと解決策