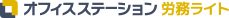お役立ち情報
労働保険料とは?負担者や計算方法、納付時期など押さえるべきポイントを徹底網羅
社労士の声から生まれたソフトだから使いやすい。オフィスステーション 労務で
入退社手続きや有期雇用の更新手続きなどの様々な労務手続きを効率化!
⇒【公式】https://www.officestation.jp/roumu/にアクセスして製品カタログを無料ダウンロード
こんにちは。人事労務クラウドソフト「オフィスステーション 労務」のお役立ち情報 編集部です。
労働者を一人でも雇用する事業者には労働保険料の支払い義務が発生します。労働保険料を算出する方法や、納付時期、納付の方法など、わかりづらい労働保険の仕組みを図で示し、初心者にもわかりやすいよう解説します。また、実際の保険料の計算に役立つExcelテンプレートも紹介します。
- 労働保険料とは?適用事業や対象となる労働者など基礎知識まとめ
- 複雑な「年度更新」の仕組みを図で解説
- 労働保険料の計算方法と計算をラクにするお役立ちツール
- 申告書が届く時期や納付期限、会計上の扱いなど
目次
労働保険料とは何か?
労働保険料とは、労働保険で納付する保険料のことをいいます。
労働保険とは「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉です。

【労災保険】
労災保険とは、労働者が業務災害や通勤災害にあった際、労働者やその遺族の保障のために保険給付をおこなう制度です。
【雇用保険】
雇用保険とは、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難になった場合に、労働者の生活と雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付をおこなう制度です。
労働保険は労働者を保護するための制度であり、保険給付は2つの制度で別個におこなわれていますが、保険料の納付は「労働保険料」として一体的に扱われます。
労働保険の適用事業主と対象となる労働者とは?
労働保険は労働者を一人でも雇用した事業に適用され、事業主には保険関係成立手続をおこなうことが法律で義務づけられています。
労働保険の対象となる労働者は以下から確認できます。
| 区分 | 労災保険の労働者の取扱い | 雇用保険の被保険者の取扱い |
|---|---|---|
| 一般労働者(パートタイマー含む) | すべて適用されます。 | 以下の労働者は、本人の希望の有無に関わりなく、適用されます。 (1) 1週の労働時間が20時間以上 (2) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること |
| アルバイト | すべて適用されます。 | 以下の労働者には適用されません。 ・4カ月以内の期間を予定しておこなわれる季節的事業に雇用される者 ・昼間学生 ・臨時内職的に雇用される者 |
| 日雇労働者 | すべて適用されます。 | 雇用保険日雇労働被保険者でない日雇労働者には適用されません。 |
| 派遣労働者 | 派遣元事業場で適用されます。 | 派遣元事業場で適用されます。 ただし、以下の2つの要件が必要です。 (1)1週の労働時間が20時間以上であること (2)反復継続して派遣就業する者であること |
| 法人の役員 | 代表権・業務執行権を有する役員には、適用されません。 | 取締役には原則として適用されません。 |
| 同居の親族 | 事業主と同居している親族は、原則として労働者にはなりません。 | |
| 海外出張者 | 適用されます。 | 適用されます。 |
| 海外派遣者 | 適用されません。 | 適用されます。 |
出典:労働保険の適用単位と対象となる労働者の範囲 | 大阪労働局
労働保険料は誰が負担する?
労働保険料のうち、労災保険料は全額を企業が負担します。このため従業員の給与や賞与から保険料を控除することがなく、給与計算の処理は不要です。
一方で雇用保険料は企業と従業員の双方が負担するので、月次の給与計算で控除しなくてはなりません。雇用保険料は毎月の総支給額に料率を乗じて計算するので、月によって雇用保険料額が異なります。
労働保険料の支払いの仕組み
労働保険料は、年に1回「年度更新」と呼ばれる手続きで支払いをおこないます。年度更新は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を期間とし、その年の保険料を概算で申告・納付すると同時に、「前年度に概算で申告した概算保険料」と「実際に支払った賃金から計算した確定保険料」の差額の精算をおこないます。
年度更新の仕組みは以下のとおりです。

確定保険料と概算保険料の算出イメージは以下のとおりです。

参考:【社労士監修】労務手続きのすべてが分かるかんたんガイド
年度更新における労働保険料の納付期間は毎年6月1日から7月10日となっています。納付期限は基本的に7月10日ですが、2022年度は7月11日までと発表されています。
労働保険料の計算方法とお役立ちExcelテンプレート
【労災保険料の計算方法】
労災保険料は以下の計算式で計算します。
労災保険料=「賃金総額(概算賃金総額)」×労災保険料率
労災保険料率は業種によって異なり、毎年改定が発表されます。2022年の保険料率は2021年から変更がなく、こちらから確認できます。
【雇用保険料の計算方法】
雇用保険料は以下の計算式で計算します。
雇用保険料=「雇用保険加入者の賃金総額(概算賃金総額)」×雇用保険料率
雇用保険料率も毎年改定が発表されます。2022年度の保険料率は以下のとおりです。
【2022年4月1日~9月30日】
| 1 労働者負担 | 2 事業主負担 | ①+②雇用保険料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (a)失業給付・育児休業給付の保険料率 | (b)雇用保険二事業の保険料率 | (a)+(b)合計 | |||
| 一般の事業 | 3/1,000 | 3/1,000 | 3.5/1,000 | 6.5/1,000 | 9.5/1,000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 4/1,000 | 4/1,000 | 3.5/1,000 | 7.5/1,000 | 11.5/1,000 |
| 建設の事業 | 4/1,000 | 4/1,000 | 4.5/1,000 | 8.5/1,000 | 12.5/1,000 |
【2022年10月1日~3月31日】
| 3 労働者負担 | 4 事業主負担 | ①+②雇用保険料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (a)失業給付・育児休業給付の保険料率 | (b)雇用保険二事業の保険料率 | (a)+(b)合計 | |||
| 一般の事業 | 5/1,000 | 5/1,000 | 3.5/1,000 | 8.5/1,000 | 13.5/1,000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 6/1,000 | 6/1,000 | 3.5/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 |
| 建設の事業 | 6/1,000 | 6/1,000 | 4.5/1,000 | 10.5/1,000 | 16.5/1,000 |
【賃金総額の計算において賃金とみなすもの/みなさないもの】
賃金とみなすもの、みなさないものは以下から確認できます。
| 賃金とみなすもの | 賃金とみなさないもの |
|---|---|
| 基本給・固定給などの基本的な賃金 | 休業補償費 |
| 超過勤務手当・深夜手当・休日手当等 | 結婚祝金・死亡弔意金・災害見舞金等 |
| 扶養手当・子供手当・家族手当等 | 増資記念品代 |
| 宿直手当、日直手当 | 私傷病見舞金 |
| 役職手当・管理職手当等 | 解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づくもの) |
| 地域手当・住宅手当・単身赴任手当等 | 年功慰労金 |
| 技能手当・特殊作業手当等 | 出張旅費・宿泊費等(実費弁償的なもの) |
| 奨励手当 | 制服 |
| 調整手当・休業手当 | 会社が全額負担する生命保険の掛金 |
| 賞与 | 財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等(労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するため事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等) |
| 通勤手当・定期券・回数券等 | 創立記念日等の祝金(恩恵的なものでなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給される場合を除く) |
| 雇用保険料その他社会保険料(労働者の負担分を事業主が負担する場合) | チップ(奉仕料の配分として事業主から受けるものを除く) |
| 住居の利益(社宅等の貸与を受けない者に対し均衡上住宅手当を支給する場合) | 住居の利益(一部の社員に社宅等の貸与を行っているが、他の者に均衡給与が支給されない場合) |
| いわゆる前払退職金(労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされるもの) | 退職金(退職を事由として支払われるものであって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるもの) |
なお、以下の厚生労働省のWebページから年度更新の申告書に記載する金額の計算に役立つExcelテンプレートがダウンロードできます。

労働保険料の会計上の扱いと勘定科目
【労働保険料の勘定科目】
給与支払時・保険料支払時の仕訳は複数パターンがありますが、もっともシンプルなのは労働保険料を全額「法定福利費」として扱う方法です。
労働保険料を全額「法定福利費」として扱う場合
| 借方 | 貸方 | |
|---|---|---|
| 概算保険料支払時 | 法定福利費 | 預金 |
| 給与支払時 | 給料 | 法定福利費 |
| 確定保険料支払時 | 法定福利費 | 預金(差額) |
そのほか、従業員負担分を「立替金」とする方法や、「前払費用」を使用する方法もあります。
労働保険年度更新申告書と納付書はどうやって手に入れる?
労働保険年度更新申告書と納付書は、毎年5月ごろに登録住所に送付されます。以下がイメージで、黄色のついた①~⑦に記入します。

まとめ
従業員を雇用する事業主は労働保険料の支払いの仕組みを理解し、正しい計算のもと保険料を納付する必要があります。しかし、年度更新は被保険者について標準報酬月額を見直す定時決定の時期と重なるため、担当者に大きな負荷をかけることになります。
従業員の情報を一元化するクラウドサービス「オフィスステーション 労務」では、普段から保存している給与情報等を利用して、自動計算・転記レスで申告書を作成し、電子申請をすることが可能です。煩雑な紙での作業にかかる時間や、郵送の時間、窓口に提出するための時間を大きく削減できるようになっています。
労務手続きをミスなくカンタンにする方法を詳しく知りたい方はこちらからダウンロード!
「オフィスステーション労務」の機能や他ソフトとの違いに関する製品カタログをお送りします!
カンタン 30秒で完了
そのほかの関連知識
-

ペーパーレス会議のメリットや効果は? Web会議ツールの導入やデジタル化の課題・進め方は?
-

労務管理とは? 必要な基礎知識や労務管理がずさんにならないようにするための方法
-

賃金台帳とは? 基礎知識や保管期間、書き方は? ダウンロード用Excelテンプレート付き
-

労働保険とは?基礎知識や企業担当者がおこなうべき手続きまとめ
-

離職票とは?離職証明書・退職証明書との違いや書き方など手続き方法まとめ
-

e-Govとは?できることや基礎知識、e-Gov電子申請のメリット・デメリットなどまとめ
-

社会保険とは?社会保険料負担の仕組みや負担料、制度の目的などわかりやすく解説
-

労災保険の休業給付を受けるには? 要件や計算方法を誰でもわかるように解説
-

労務の内製化に失敗しないための方法とは?
-

労働保険料とは?負担者や計算方法、納付時期など押さえるべきポイントを徹底網羅