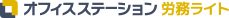お役立ち情報
社会保険とは?社会保険料負担の仕組みや負担料、制度の目的などわかりやすく解説
社労士の声から生まれたソフトだから使いやすい。オフィスステーション 労務で
入退社手続きや有期雇用の更新手続きなどの様々な労務手続きを効率化!
⇒【公式】https://www.officestation.jp/roumu/にアクセスして製品カタログを無料ダウンロード
こんにちは。人事労務クラウドソフト「オフィスステーション 労務」のお役立ち情報 編集部です。
社会保険(社保)は国民の生活のセーフティネットとして機能する制度の一つ。企業は自社で負担する社会保険料と、従業員から徴収した社会保険料を納めなければなりません。社会保険料とは何か、制度の仕組みや目的、使用用途、保険料の計算方法などをまとめました。
- 社会保険(社保)とは何か?
- 誰が社会保険料を負担するのか
- 社会保険の適用拡大の詳細、アルバイトやパートタイムが負担するケースは
- 社会保険料の計算方法と負担額
目次
社会保険とは?目的や使用用途など基礎知識まとめ
【社会保険とは?】
社会保険とは、国民の生活の安定を支えるセーフティネットである社会保障制度の一つです。社会保障制度は社会保険のほか、「社会福祉」「公的扶助」「保険医療・公衆衛生」から構成されます。

このうち社会保険は、国民がケガ、出産、死亡、老齢、障害、失業など生活の困難をもたらすさまざまな事故(保険事故)に遭遇した場合に、一定の給付をおこない、その生活の安定を図ることを目的とした強制加入の保険制度をいいます。
また社会保険を大別すると以下のように分けられます。
| 年金保険(厚生年金/国民年金) | ・20~60歳のすべての居住者が国民年金に加入。
・原則、65歳から老齢給付を支給。 ・障害給付、遺族給付についても支給。 |
| 医療保険(被用者保険/国民健康保険) | ・すべての居住者が加入。
・現物給付が原則。一部現金支給あり。 |
| 雇用保険 | ・原則、すべての被用者が加入。
・失業した場合、教育訓練を受けた場合に給付。(倒産・解雇などによって失業した場合、最高330日給付) |
| 労災保険 | ・原則、労働者を使用するすべての事業が加入。
・労働災害が発生した場合に、労働者などに対して給付。(現物給付、現金給付) |
| 介護保険 | ・40歳になると介護保険への加入が義務づけられます。
・介護が必要になった65歳以上の高齢者、および40歳から64歳までの医療保険加入者のうち特定疾病で要介護と認められた場合に給付。 |
【社会保険は何に使われるのか?】
厚生労働省によると、社会保障給付のうち、44.9%が年金、31.1%が医療、24%が福祉その他となっています。その他の内訳としては介護が10%、子供・子育てが7.4%です。また、社会保険給付はすべてが保険料でまかなわれるのではなく、41.3%は公費を財源としています。

参考:給付と負担について
社会保険の持つ3つの意味と国民健康保険の違い
社会保険という言葉は広義・狭義で計3つの使い方があります。

広義の社会保険は、前述のとおり社会保障制度を構成する仕組みの1つであり、その内容は大きく「被用者保険」「国民健康保険」「国民年金」の3つに分けられます。そして社会保険という言葉を狭義で使う場合の多くは、会社員が加入する「被用者保険」という意味合いになります。
日本はすべての国民が公的医療保険に加入することになっているため、被用者保険に加入しない方は「国民健康保険」に加入することとなります。このため、社会保険という言葉が狭義としての意味合いで使われる場合、「社会保険は会社員のための保険、国民健康保険は会社員以外のための保険」という文脈が一般的です。
狭義の社会保険と国民健康保険の違いは以下のとおりです。
| 社会保険(狭義) | 国民健康保険 | |
| 対象となる方 | 会社員・公務員とその扶養家族 | 個人事業主・農業・漁業従事者・パートタイム・アルバイト等 |
| 保険者 | 全国健康保険協会・健康保険組合 | 都道府県・市町村・各種国民健康保険組合 |
| 保険料の支払い | 給与から天引き(半額は勤務先負担) | 全額自分で支払う |
| 医療費 | 原則3割負担 | 原則3割負担 |
なお、被用者保険には「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5つがあり、このうち「健康保険」と「厚生年金保険」の2つを「社会保険」と呼ぶ場合もあります。一言で「社会保険」といっても、指し示す内容がケースバイケースで異なるため、どの意味合いで使われているのかには注意が必要です。
社会保険の加入要件と保険料の負担が必要になる年収
社会保険には加入条件が存在します。特に狭義の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件は法改正により段階的に変更されているため、企業の人事・労務担当者は注意が必要です。
【従来の要件】
- フルタイムで雇用されている従業員
-
.週の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上かつ1カ月間の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3上である者
【新に加わった従業員の要件】
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が2カ月超見込まれること
- 賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
- 学生でないこと
新たな条件が加わることで、これまでは社会保険の適用対象外だったパートタイムやアルバイトについても、社会保険の対象となります。ただし、新たな条件が適用されるのは2022年11月時点で「従業員数100人超(101人以上)規模」の事業所となっています。事業所の規模要件については2024年10月にも改正がある予定です。
【規模要件による適用拡大のスケジュール】
2022年6月~:従業員数501人超の企業(500人以下でも労使合意により適用拡大が可能)
2022年10月~:従業員数100人超(101人以上)規模
2024年10月~:従業員数50人超(51人以上)規模
アルバイトやパートタイムとして働く方の中には、社会保険の被保険者の扶養家族として認められる被扶養者(健康保険法3条7項)となり、社会保険料を徴収されない方もいます。社会保険の被扶養者は原則的に以下の条件を満たす方をいいます。
・年間収入が130万円未満
・被保険者の年間収入の2分の1未満である場合
しかし、社会保険の適用拡大がおこなわれたことで、上記の収入の基準を満たす場合でも、働く企業の規模によっては年収106万を超える場合は保険料の支払いが必要となるため注意が必要です。
人事・労務担当がおこなう社会保険の手続き
社会保険に関する手続きにはさまざまなものがあり、以下がその一例となっています。
・事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき
・事業所の名称・所在地を変更するとき
・新しく従業員が入社とき
・従業員が退職するとき
・従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったとき
・従業員の報酬月額の届出を行うときの手続き(算定基礎届・月額変更届等)
・従業員に賞与を支給したとき
・従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したとき
・従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したとき
社会保険手続きには、従業員の入退社に伴うものがあれば、結婚・出産といったライフイベントに伴うもの、従業員の年齢に伴うもの、年に一度同時期に発生するものなどがあります。
毎年発生する手続きについてはノウハウが蓄積されますが、発生頻度の少ない社会保険手続きは、つい見逃してしまったり、やり方を忘れがちです。そんな多岐に及ぶ社会手続きの年間スケジュールや発生タイミング、届出の書き方や提出先といった必要知識は、以下のeBookからまとめて確認できます。
オフィスステーション|労務手続きのすべてが分かるかんたんガイド
社会保険料の計算と支払う金額
企業の人事・労務担当者は、社会保険手続きだけでなく、保険料の徴収と納付もおこなわなければなりません。企業が扱う社会保険の種類は5つあり、それぞれの保険によって保険料の計算も変わるため、注意しましょう。
社会保険料には、以下の5種類が含まれます。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 介護保険料
- 雇用保険料
- 労災保険料
【社会保険料の計算】
上記5つの社会保険料のうち、1~4は従業員と会社が折半で、5については会社が全額負担します。1~4の保険料は従業員給与から天引きされます。その際の従業員負担額は以下の計算式から求められます。
・健康保険料
標準報酬月額×保険料率÷2
※健康保険料率は毎年改定され、最新のものはここから確認できます。
・厚生年金保険料
標準報酬月額×保険料率÷2
※厚生年金の保険料率は2017年以降18.3%で固定されています。
・介護保険料率
標準報酬月額×保険料率÷2
※介護保険料率は毎年改定され、最新のものはここから確認できます。
・雇用保険料率
給与額×保険料率
※雇用保険料率は労働者負担と事業主負担で異なります。2022年度の雇用保険料率については、ここから確認することが可能です。
なお、標準報酬月額とは従業員の月々の給与を1~50の等級にわけて表すものであり、社会保険料の計算を簡便化するために用いられます。
社会保険まとめ
社会保険国を支える重要な制度であり、企業の人事・労務担当者は内容を理解し、従業員を社会保険に加入させ、保険料を納めなければなりません。しかし、社会保険適用の拡大など、近年は法改正により社会保険の加入要件が複雑化しています。正しく手続きするためにも、それぞれの手続きの内容・加入要件・様式・提出期限などをしっかりチェックしておきましょう。
労務手続きをミスなくカンタンにする方法を詳しく知りたい方はこちらからダウンロード!
「オフィスステーション労務」の機能や他ソフトとの違いに関する製品カタログをお送りします!
カンタン 30秒で完了
そのほかの関連知識
-

バックオフィス業務で残業が発生しやすい要因5つと解決策
-

社会保険の扶養条件とは? 対象者の年収額や年金受給者の扱いなどをわかりやすく解説
-

離職票とは?離職証明書・退職証明書との違いや書き方など手続き方法まとめ
-

労務の内製化に失敗しないための方法とは?
-

賃金台帳とは? 基礎知識や保管期間、書き方は? ダウンロード用Excelテンプレート付き
-

gBizID(GビズID)とは? できることやe-Govとの違いなどを解説
-

労務管理とは? 必要な基礎知識や労務管理がずさんにならないようにするための方法
-

労災保険の休業給付を受けるには? 要件や計算方法を誰でもわかるように解説
-

労働保険料とは?負担者や計算方法、納付時期など押さえるべきポイントを徹底網羅
-

3分で読める! パワハラ防止法の概要と具体策