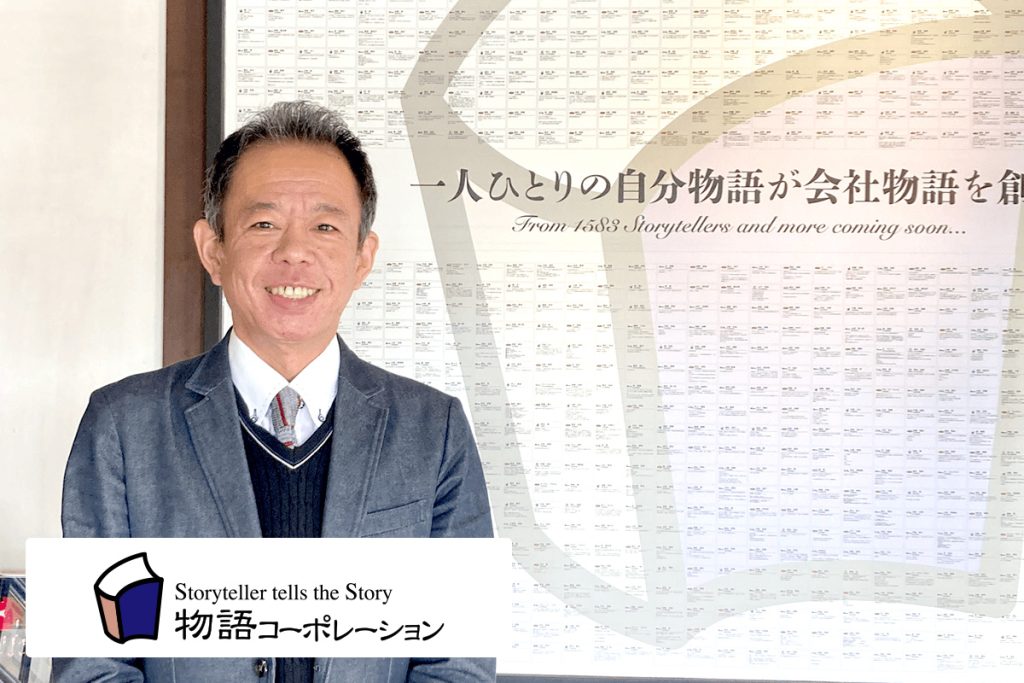- ①高年齢雇用継続給付など紙の手続きが多く、毎月膨大な書類処理に追われていた
- ②届出のチェックや行政への提出、公文書の返送に時間と労力がかかっていた
- ③限られた人数で残業しながら対応し、ミスや再提出も頻発していた
- ①労務手続きの電子化で月4,340分(約72時間)の業務時間を約97%削減できた
- ②押印や郵送作業が減り、担当者の負担と残業時間が大きく軽減した
- ③書類の電子保存で保管スペースと郵送コストの両方を削減できた
- ④業務改善の成功体験から、社内全体でデジタル化への意識が高まった
600名分の高齢者継続給付申請で、頭を抱える状況に
はじめに、事業内容と、総務部の体制ついて教えてください。
市川さま :
四国旅客鉄道株式会社は、四国エリアで鉄道事業を中心に、旅行業と関連事業を展開しています。従業員数は契約社員を含めて約2,600名で、運転士や車掌といった現場職の従業員が多く在籍しています。
私は本社の総務部に所属しており、その中の勤労課で雇用保険や福利厚生制度の運用を担当しています。勤労課、福利厚生部門の担当スタッフは4名で、ハローワークなどへの各種届出業務はすべて勤労課が担っている状況です。

労務手続きについて、システム導入前はどのような方法で対応されていたのでしょうか?
市川さま :
2020年頃までは、雇用保険や社会保険に関する届出はすべて紙で提出していました。
たとえば定年後再雇用者に支給される「高年齢雇用継続給付」の申請書類や、育児休業給付金の申請、新入社員の雇用保険被保険者資格取得届、退職者の離職証明書など、すべての手続きが紙ベースでした。
約2,600名分の労務手続きを紙で対応されていたのですね。当時の状況を教えてください。
市川さま :
紙手続きの業務量は非常に多く、「従業員本人から必要書類を紙で提出してもらう」「勤労課でチェックして会社の代表印を押印する」「ハローワークに持参する」という流れで1カ月が過ぎてしまうほどでした。
特に大変だったのが高年齢雇用継続給付の申請業務です。対象者が最大で600名ほどおり、2カ月に一度、全員分をまとめて申請する必要がありました。
そのほか、育児休業給付や離職票の発行なども毎月発生しますので、何度もハローワークに通い、各種書類を提出していました。当然、ミスや不足があれば差戻しになります。昔は申請書類に本人のハンコ(印鑑)が漏れているケースもあり、そのたびに頭を抱えるような状況でした。
こうした煩雑な業務を、当時は限られた人員で何とか回しており、足りない部分は基本的に残業で対応するしかありませんでした。
「高年齢継続給付を一括申請できる仕組み作り」が喫緊の課題に
紙を中心とした手続き業務を、どのようなきっかけで見直すことになったのでしょうか?
市川さま :
きっかけとなったのは、2020年4月から一部の社会保険や労働保険の手続きについて、特定法人に電子申請が義務化されたことです。
当社も対象でしたので、「それなら、この機会に手続きを電子化しよう」と動き出しました。まず検討したのは、政府が提供している電子申請システム「e-Gov」です。ところが、実際に使い方を調べていく中で、いくつかの機能面での課題が見えてきました。
たとえば、当社で件数が最も多い「高年齢雇用継続給付」について、e-Govでは一人ずつ手入力する必要があり、「とても実務では使えない」と感じたんです。
何百人分もの申請を一件ずつ入力するのは現実的ではありません。そこで「高年齢継続給付を一括で申請できる仕組みはないか?」とほかのシステムを探し始め、その中で出会ったのが「オフィスステーション 労務」でした。
参考:「オフィスステーション 労務」の一括申請機能について
「オフィスステーション 労務」では、「資格取得時決定」や「喪失届」、「被扶養者異動届」、「高年齢雇用継続給付手続」、「育児休業給付手続」など、日常的に発生する主要な手続きについて、一括での申請が可能です。
これにより、複数人分の情報をまとめて処理できるため、個別入力や提出にかかる手間が大幅に削減され、担当者の業務負担を軽減します。

数百名規模の給付金申請を一括で電子化できるシステムとなると、選べる選択肢も限られてきそうですね。サービスを比較し決定するにあたって、決め手になったポイントを教えてください。
市川さま : 決め手になったのは、コスト面のメリットと、営業の方のレクチャーが非常に丁寧であったことです。無料トライアルにおいても、実務を通じてじっくり検証できたのはありがたかったですね。
72 時間かかっていた手続きを97%削減へ
導入にあたって、社内の承認を得るために工夫されたことはありますか?
市川さま :
あらかじめ、紙で手続きした場合と、オフィスステーションを使って電子申請した場合とで、どれだけ業務時間に差が出るかを比較した資料を作成して提案しました。この方法でスムーズに進めることができました。
たとえば、高年齢継続給付の手続きでは、従来は2カ月あたり延べ4,340分(約72時間)かかっていた作業が、オフィスステーションを使えばわずか110分で済む、という試算結果を示しました。
この時間には、公文書の受け取り・仕分け・送付、賃金台帳の印刷・添付・提出まで、すべての工程を含んでいます。
そのうえで「2ヵ月あたり約72時間の業務削減でき、人件費や郵送費、交通費などのコスト削減を考慮すると、十分な費用対効果を見込めます」と伝えたところ、経営層からも「それなら導入しよう」とすぐに承認されました。
実際に導入されたことで、試算通りの時間短縮効果は得られましたか?
市川さま :
はい、おかげさまで、試算どおりの効果が出ています。
対応にかかる時間は約1/40にまで圧縮され、担当者の残業も大幅に減りました。また、ハローワークへ持参する必要がなくなったため、交通費の負担もゼロです。
定性的な面でも、導入後は良い変化がたくさんありました。
たとえば、厚生年金の月額変更届や資格取得届、算定基礎届などの年金機構への各種手続きも、すべてオフィスステーションから電子申請できるようになりました。
以前はCDで提出し、紙で返送されるという流れでしたが、これらがなくなり、物理的な管理の負担も軽減されています。
また、ハローワークとのやり取りがオンラインに移行したことで、電話や移動に業務を中断されることも減り、担当者が集中して作業に取り組めるようになりました。
以前は申請の締切が近づくたびに対応に追われ、残業が続くこともありました。日中も電話が鳴るたびに作業が止まってしまうことが多かったのですが、今ではそうしたストレスからも解放されています。
導入後の運用も順調に進んでいるようですね。現場での反応はいかがでしょうか?
市川さま :
はい、大きなトラブルもなくスムーズに定着したと思います。
もともと紙文化だった分、最初は戸惑う場面もありましたが、「オフィスステーション 労務」のシステムは非常にシンプルで使いやすかったですね。画面の指示に沿って順番に項目を埋めていくだけで申請が完了しますし、途中で入力漏れがあればエラーメッセージが出るので、特に迷うことなく操作を習得できました。

残業削減で生まれたゆとりと現場の意識変化とは
業務時間の削減以外に、サービス導入によって得られた変化があれば教えてください。
市川さま :
慢性的だった残業が解消されたことで、気持ちに余裕が生まれたのは間違いありません。
なかでも印象的だったのは、現場の従業員の意識の変化です。
高年齢継続給付の電子申請をうまく導入できたことで、担当メンバーから「これはすごい」「ほかの手続きも電子化できるのでは?」「もっと効率的な方法があるのでは?」という前向きな声が上がるようになりました。また労務手続きに限らず、社内全体でデジタル化に対する前向きな姿勢が芽生えてきたと感じています。
従業員とのコミュニケーション面でも変化がありました。
以前は、紙の決定通知書を各事業所に郵送し、「従業員に手渡してください」とお願いしていましたが、今ではPDFデータをメールで本人に直接送る方法に切り替えています。
これにより、「書類が届いていない」と言われた際も、「もう一度送りますね」とすぐに対応できるようになりました。実際に従業員の方から「メールでもらえる方が助かる」と言っていただけたこともあり、紙の郵送によるタイムラグや行き違いがなくなったことで、現場の安心感にもつながっていると感じています。
誰もがワークライフバランスを大切にできる会社へ
最後に、人事・総務の業務において大切にされていることや、今後の展望をお聞かせください。
市川さま :
JR四国グループの事業計画では「人材の確保・育成・定着施策の強化」が掲げられており、総務部門としても従業員が安心して働き続けられる環境づくりに力を入れています。
私が担当する勤労課では、特に育児や介護といった事情を抱える従業員が仕事と家庭を両立できる制度づくりを進めています。
「柔軟な働き方」の実現に向けて動かれているのですね。一方で、「柔軟な働き方」が難しい職種もあると思うのですが、そのあたりはどのように配慮されていますか?
市川さま :
確かに、運転士や車掌などの現場職はリモートワークが難しいため、柔軟な働き方をどう実現するかが、依然として大きな課題となっています。
そこで当社では、たとえば泊まり勤務が難しい従業員には専用の勤務ルートを設定するほか、業務に支障が出ないよう人員を増やすなど、現業部門と連携しながら柔軟な勤務体制の構築に取り組んでいます。
こうした取り組みの一環として、国が定める「産後パパ育休」とは別に、誰でも利用できる「育児産後休暇」を制度として整備しました。「休暇」なので「育児休業」よりも柔軟に休みを設定でき、当社での利用者も多いです。
また、現場の駅長や区長といった管理職が「遠慮せずに取得していいよ」と声をかけてくれていることも、制度が形式的なものにとどまらず、実際に機能している大きな要因だと感じています。
そのほか、定着施策として取り組まれていることがあれば教えてください。
市川さま : 若手社員の定着率向上を目的とする取り組みとして、社宅・寮の整備や家賃補助の見直しも進めています。また昨年は初めて社内アンケートとしてエンゲージメントサーベイを実施しましたが、その中で「オフィスが汚い」といった率直な声が寄せられ、人事部門としてもハッとさせられました。現在はその意見をもとに、オフィス環境の改善にも取り組み始めているところです。
参考:従業員サーベイについて
近年、従業員のエンゲージメント向上や離職防止を目的に、従業員サーベイに取り組む企業が増えています。
「オフィスステーション タレントマネジメント」では、このサーベイ機能を標準搭載しており、従業員の意識や満足度を可視化することが可能です。サーベイ結果をもとに課題の早期発見や職場環境の改善につなげることで、働きやすい職場づくりを支援します。

サービスURL:https://www.officestation.jp/talentmanagement/
現場の声を聞き、制度として落とし込んだ上で、しっかり周知することで、「誰でも安心して制度を使っていい」と思える環境を構築されているんですね。
市川さま :
はい。私たちは、このような、「従業員が安心して、長く働き続けられる会社づくり」に、これからも貢献していきたいと思います。
そしてそのためには、日々の業務をいかに効率化していくかが大切です。「オフィスステーション 労務」を導入したことで、私たち総務部は、以前よりも余裕を持って働けるようになりました。新たに余裕ができた時間やエネルギーを、これからはより一層、従業員の皆さんの働きやすさや定着につながる施策に充てていきたいですね。
本日は貴重なお話をありがとうございました!