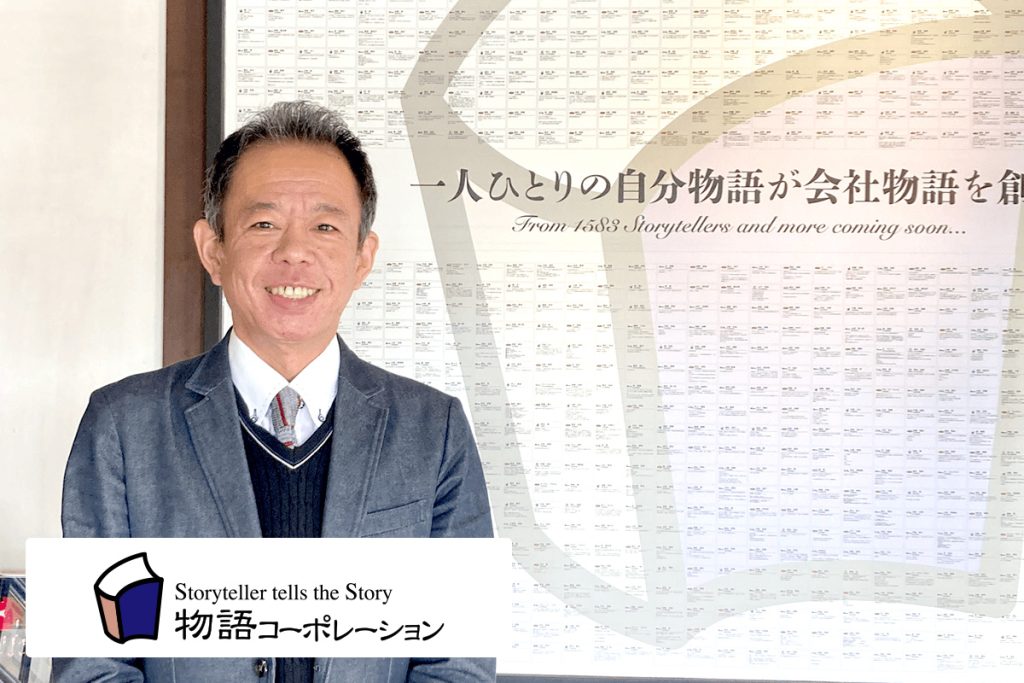- ①入退社や契約書、年末調整など、あらゆる手続きが紙ベースで非効率的
- ②店舗従業員への郵送業務や封入・印刷作業が膨大で、負担が大幅に増加
- ③少ない担当者で全従業員の対応を担っており、業務量過多状態
- ①紙・郵送業務を大幅削減し、2~3週間かかっていた手続きを最短2〜3日に短縮
- ②独自運用に合わせた「申請の電子化」で、現場の申請精度と対応スピードが向上
- ③入退社手続きを1名体制で運用できる仕組みを構築し、手続き業務を約70%効率化
グループ全体の管理業務を支える人事・労務部門の現場
はじめに、事業内容と荒田さまの担当業務について教えてください。
荒田さま :
株式会社ルックホールディングスは、アパレル事業を軸に複数のブランドを展開する持株会社で、全国に約300店舗を構えています。グループ各社が企画から販売までを担い、一体となって事業を推進しています。
私は現在、人事総務部 人事課に所属しており、課長として人事・労務・採用を含む人事業務全般を担当しています。人事課は私を含めて7名体制で、うち労務担当が2名、採用担当が1名、一般事務担当が2名です。一般事務の2名は、ハローワークへの手続きなど、本社のシステムを使った各種事務業務を中心に担当しています。
紙運用の良さは「カスタマイズ性」と「サポート体制」で引き継げる
人事・労務領域のDX推進を始める前は、どのような課題がありましたか?
荒田さま :
最も大きな課題は、「紙と手作業が前提の業務体制」でした。入退社や契約書の発行、各種申請など、あらゆる手続きが紙ベースでおこなわれ、書類の郵送や封入、回収・確認まで多くの手間と時間がかかっていたのです。
とくに契約更新や年末調整の時期は作業量が一気に増え、事務担当を含めたメンバー全員が対応に追われる状況でした。
記入ミスや未記入の書類も頻繁に見受けられ、郵送中の紛失が発生することもありました。
こうした「アナログ中心」の業務に次第に限界を感じるようになり、電子化やシステム導入の必要性を強く意識するようになったのです。

人事・労務業務の電子化にあたって、システムを選ぶ際に重視したポイントはどこでしたか?
荒田さま :
複数のサービスを比較検討しましたが、重視したのは「必要な機能が網羅されていること」「直感的な操作性」「サポート体制の充実」でした。
そこで特に評価が高かったのが、「オフィスステーション 労務」です。
特に現場の従業員はデジタルが苦手な方も多いため、「オフィスステーション 労務」の誰でも使いやすいUIや、視認性の高いシンプルな画面設計は大きな決め手となりました。
そして、個人的にとても助かったのは、「サポート体制」ですね。
社内の担当者は私を含めてデジタルが得意ではありませんでしたので、オフィスステーションの導入支援担当者が、導入前後の疑問や不安にきめ細かく対応してくれる点が心強かったです。
サポートでは、具体的にどのようなことをご相談されたのですか?
荒田さま :
システムを導入する際、企業ごとに細かな調整が必要になるのは当然のことですが、当社も例外ではありませんでした。
当社はホールディングス企業ということもあり、子会社ごとに運用が異なるため、それぞれに応じたきめ細かな対応が求められます。グループ会社ごとに異なる契約書や申請書が必要なほか、当時は「給与明細に独自の支給項目や通知文を同封する」など、紙ならではの柔軟な運用をおこなっていたため、それを電子化でどう再現するかが大きな課題でした。
そのときに担当の方が、当社の運用に合わせたレイアウトやフローを丁寧に教えてくださったのは、とても心強かったです。紙で差し込んでいた内容を、PDFにしてメッセージとして添付するなど、さまざまな工夫が必要でしたが、最終的にはかなり柔軟なカスタマイズが実現できました。
また、導入後も電話でサポートデスクにつながる環境があるのはありがたいですね。チャット対応のみのサービスが多い中、実際の声を聞きながら進められる安心感は大きかったです。
参考情報:「オフィスステーション 労務」導入支援サービス

「オフィスステーション 労務」では、専門スタッフが定期的なミーティングを通じて、お客さまに最適な運用方法をご提案する『導入支援サービス』(※別料金)をご用意しています。
オリジナルマニュアルの作成や社内研修の実施など、お客さまの状況やご要望に合わせたサポートをおこない、バックオフィス業務のDX推進を丁寧にお手伝いいたします。
手続き業務時間は70%短縮、担当者は2人→1人に
「オフィスステーション 労務」導入後の変化についても教えていただけますか?
荒田さま :
当社は全国に多くの店舗と従業員がおり、月10~15件ほどある入退社のほか、異動、再雇用といった手続きが日常的に発生しています。また退職理由や雇用形態もさまざまで、たとえば定年退職後に子会社へ再就職するケースも多く発生します。
「オフィスステーション 労務」導入後は、これらの手続きがすべてオンラインで完結できるようになり、大きな業務効率化につながっています。
たとえば、これまで1件の入社手続きが完遂するまでに2~3週間ほどかかっていたところ、今では早ければ2~3日で完了することもあります。担当者からも「時短になった」「戻ってくるのが早い」といった声が上がっています。
以前は入社書類を紙で郵送し、本人に記入・返送してもらう必要があり、手続きの進捗は従業員次第でした。今ではスマホから必要書類を随時アップロードしてもらえるようになり、書類の回収も非常にスムーズになりました。
参考情報:「オフィスステーション 労務」従業員画面(スマホ)

「オフィスステーション 労務」では、入社手続きなどで従業員が提出する情報を、PCやスマホから手続きするだけで完結できます。画面はシンプルで見やすく、PC操作に不慣れな方でも直感的に操作できる設計になっています。
現在、入退社の手続きは何名体制でおこなっているのですか?
荒田さま :
実は今、入退社に関わる労務担当者は1人だけで、入退社手続きから離職票の発行まで、すべてその1人が担っています。以前は雇用形態ごとに業務を分けていて、販売職を1人、内勤社員を別の1人が対応していたのですが、担当者の異動もあり、現在の体制になりました。
以前の2倍の業務量をこなしてくれている当人は、本当に頑張ってくれていると思います。そして、「これまで2人で対応していたことを1人で対応できるようになった」という電子化の成果は、人材不足が深刻化するこれから時代に、ますます重要になると考えています。
申請フォームの電子化で業務効率が大きく向上
「オフィスステーション 労務」で、独自に工夫して利用している点がありましたら教えてください。
荒田さま :
これまで紙で提出してもらっていた慶弔関連の手続きについて、「ワークフロー」機能を活用しています。たとえば、結婚や離婚、身内の不幸などに関する申請などですね。
また、店頭スタッフは異動や職位変更が多く、従来の「身上変更申請」では対象項目が広すぎて、必要な情報だけを簡潔に申請するには不向きでした。
そこで、店舗やブランドの異動、職位の変更といったケースに対応するため、「所属変更届」という専用の申請フォームをオリジナルのワークフローとして作成しました。
以前は1枚の紙でまとめて対応していた内容を、目的ごとに分けて電子化したことで、業務効率が大きく向上しました。現在、この申請フォームは非常に多く利用されています。
参考情報:「オフィスステーション 労務」ワークフロー機能

「オフィスステーション 労務」のワークフロー機能では、用途に応じて11種類のフォーム項目を自由に組み合わせ、申請書類を簡単に作成できます。
申請はスマホやPCから簡単におこなうことができます。
ワークフローの例(「制服申請」の場合)

電子化やその工夫による「現場の意識」や「組織風土」の変化はありましたか?
荒田さま :
はじめのうちは、紙に慣れていたスタッフから戸惑いや不安の声がありましたが、実際に電子化を体験するうちに、「意外と簡単だった」「スマホから手続きできて便利」といった前向きな声が増えてきました。
「オフィスステーション 労務」はUIがシンプルで、必要な項目を上から順に入力するだけで申請が完了します。入力ミスがあった場合もエラーで通知されるため、操作に不慣れなスタッフでも戸惑うことなく使いこなせている印象です。
人事・労務DXの先にある、人と組織の“これから”
業務効率化やDX推進を経て、現在注力している取り組みや、今後取り組みたいテーマについてお聞かせください。
荒田さま :
特に課題意識を持って取り組んでいるのは、「ワーク・ライフ・バランスの推進」です。
業務をできる限り仕組み化・デジタル化することで、限られた人員でも従来と同等、あるいはそれ以上の成果が出せる体制を整えれば、自然と残業も減らせると考えています。
一方で、若手社員の業務負担が増える傾向にあり、やりがいとプレッシャーのバランスが難しいと感じています。
定年を迎えるベテラン社員が増えるなかで、若手に裁量ある仕事を任せる機会が増えているのは事実です。ただ、その分、「思っていたより大変だった」「このまま続けていけるのか」と不安を抱えることもあり、人事としては社員の思いや悩みを安心して吐き出せる場づくりが必要だと感じています。

具体的に検討している、またはすでに取り組まれていることがありましたら教えてください。
荒田さま :
当社では、自己啓発や資格取得に関する支援が比較的整ってきているので、今後の取り組みとしては、従業員がリフレッシュできるようなヘルスケアや福利厚生の制度の充実を検討しています。
従業員の健康に直結するような取り組みについて、他社の事例を参考にさせていただきつつ、デジタルのハード面だけでなく、「人」としてのソフト面も含めて、従業員自身が「働きやすさ」や「楽しさ」を実感できるような制度にしていきたいという思いがあります。
実際に制度を動かすとなると大きな変化が必要なので、簡単ではありませんが、じっくり取り組んでいきたいと考えています。
本日は貴重なお話をありがとうございました!